
ロボットに仕事を奪われる。そんな不安が語られて久しい中で、ロボティクススタートアップ・MUSEは、あえて逆の思想を掲げています。
「ロボットは、人の創造力を解き放つ存在であるべきだ」──そう語るのは、株式会社MUSE 代表の笠置泰孝氏。幼少期の原体験からくすぶり続けた起業家としての想い、ロボットビジネスへの道、そして創業後に直面した数々の壁。人と技術の共創を本気で目指す笠置氏に、その思想の背景と未来へのビジョンを聞きました。
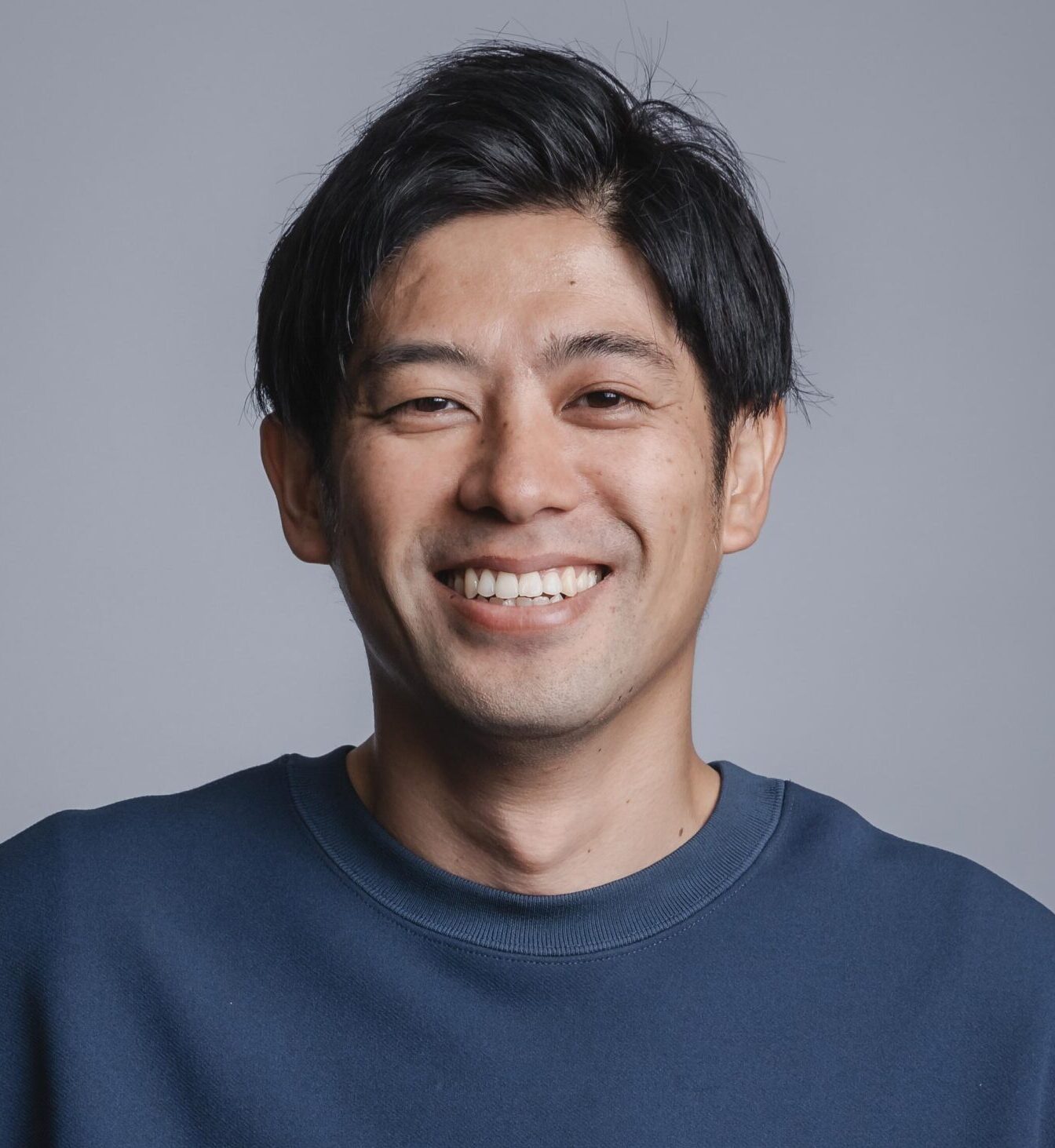
代表取締役
笠置 泰孝氏
一橋大学商学部卒業後、新日本有限責任監査法人、ゴールドマン・サックス証券で勤務。その後ZMPにて物流ロボットCarriRoシリーズの立ち上げから量産拡販まで7年間従事。延べ国内で300社以上の倉庫又は工場に導入。 2022年4月にMUSEを創業。

株式会社MUSE
https://www.muse-gr.com/
- 設立
- 2022年08月
《Mission》
ロボットで世界の人々にインスピレーションを。
《事業分野》
ロボティクス・小売・AI
《事業内容》
MUSEは、人の創造性やコミュニケーション能力といった本来の価値に光をあてる“共創型ロボット”を開発するスタートアップ。時間帯に応じて複数の業務を柔軟に担う「マルチユース型ロボット Armo(アルモ)」を軸に、国内外の小売現場への導入を進めている。単なる省人化ではなく、「人を輝かせる存在」としてロボットが社会に溶け込む未来を目指す。2024年には米国法人を設立し、グローバル展開にも注力している。
- 目次 -
経営者としての父の“光と影”、その両方を見てきた
幼少期にお父様の経営者としての姿を見て、強い影響を受けたとお聞きしました。
父は自ら会社を興して経営していたんですが、常に順調というわけではなく、むしろ逆風の方が多かった印象です。規制の変化や業界の波で苦労している姿もたくさん見てきました。一方で、経営者としての覚悟やかっこよさ、社会から必要とされているという実感を持って仕事をしている父の姿も、ちゃんと記憶に残っています。
経営者としての“苦しさ”と“やりがい”、その両方を見てこられたんですね。
はい。だからこそ、「自分が見返してやりたい」という思いもあったし、「経営者って面白そう、かっこいい」とも思っていました。ポジティブな感情も、悔しさのような気持ちも、どちらも自分の中に原体験として残っていて、それが「将来、自分も経営者になる」という意志に繋がっていったんだと思います。
万博で出会ったロボットが、起業家としてのスタート地点になった
その後、ロボットに興味を持ったのはどんなキッカケがあったのでしょうか?
大学2年のときに友人と愛知万博に行って、ロボットパビリオンを見たんです。それがすごく衝撃的で。「これは絶対に将来の社会に不可欠になる」と直感しました。
その時点でロボット事業に進む決意をされたのですか?
いや、まだ何をやるかまでは定まらず、ずっとくすぶってましたね。ロボットの事業をやってみたいけれど何をすればいいかわからない。エンジニアの知り合いもいないし、文系出身だし技術も分からない。そんな状態で、監査法人に入り、投資銀行に移って……10年くらい悩み続けた感じです。

技術の壁を知らなかったから、顧客の声を信じられた──現場発想が導いたプロダクト開発
最初にロボット業界に関わったのは?
転機は、あるベンチャーキャピタルの勉強会でした。自分で温めていたロボットのアイデアをプレゼンして、「やっぱりこの分野で挑戦してみたい」と気持ちが固まりました。
その後、スタクラ(当時アマテラス)を通じて転職活動をするなかで、自動運転系のスタートアップと出会い、ビジョンに共感してジョインを決めたんです。物流ロボットの新規事業を任せてもらえることになって、完全に未経験の状態からのスタートでした。この経験が、後に自分でMUSEを立ち上げる決意を固める大きな原動力にもなりました。
未経験での転職だったのですね。どうやって事業を動かしていったんでしょうか。
正直、技術のことは全然わからなかった。でもだからこそ、お客さんの声を真っ直ぐに聞けたんですよね。これが欲しい、これがないと困る──それを聞いて、社内のエンジニアに「これをこのタイミングで作れたら、売れるよ!」って本気で伝える。技術の限界を知らないからこそ、遠慮なく言えたし、顧客視点に立てたのだと思います。
人を支え、輝かせるために──MUSEが目指すロボットの在り方
MUSEの掲げる“人にインスピレーションを届けるロボット”という思想について、詳しく聞かせてください。
これまでのロボットって、基本的に“完全自動”や“無人化”を目的としてきたと思うんです。でも、そればかりが進んだとき、本当に人はそれを歓迎できるのか?っていう疑問があるんですよね。
ロボットが人間の仕事を“奪う存在”になってしまうかもしれない…。
そうなんです。MUSEでは、“ロボットを使う人がどう変わるか”という視点をすごく大事にしています。たとえば品出しや在庫確認のような作業をロボットが担うことで、スタッフの方が本来の力──創造性とか、ひらめき、優しさ、コミュニケーションといった、人間だからこそ出せる価値を発揮できるようにしたい。“人を支えるためのロボット”であり、“人を輝かせるための存在”でありたいと思っています。
ロボットの存在意義が“人の変化”にあるというのは、とても印象的です。
そこが、単なる効率化との違いですね。単に「作業が早くなった」で終わらせず、「このロボットがいることで、自分はもっと価値ある仕事ができる」と思えるような。人がロボットによって“自分の役割を再定義できる”ような世界を目指しています。

“1台=1機能”の常識を壊す──柔軟に働くロボットが現場を変える
開発しているプロダクトについて教えてください。
「Armo(アルモ)」という名前で、時間帯に応じて役割を切り替えられるロボットを開発しています。午前は品出し、午後は販促支援といったように、1台で複数の業務に対応できるのが特徴です。
1台で複数の役割をこなせるんですね。
はい。従来は清掃用、警備用など機能ごとにロボットが分かれていましたが、たとえば小売店では、1日の中で業務がどんどん変化します。だからロボットも、時間に合わせて柔軟に役割を変えられる方が合理的だと考えました。
実際に現場で使われるには、どんな工夫が必要でしたか?
Armoには“目”の役割を果たすカメラがついていて、棚の商品を撮影し、在庫の減少を検知して担当者に知らせたり、人と同じようにスイングドアを押して通れる設計も取り入れています。ただ、人が働く空間では、効率一辺倒ではダメなんです。たとえば人とすれ違う時は、ギリギリを通ると怖がられたり、事故のリスクもある。あえて少し距離をとって動くなど、共存のための細やかな工夫が必要でした。
そうした配慮は、どこから生まれたんでしょう?
現場に何度も何度も足を運び、観察して、何が自然かを確かめるしかありません。どこで引っかかるか、どんな動きが安心感につながるか──地道な試行錯誤の繰り返しでした。現場が好きなんですよね。そういう積み重ねが、“人と共に働くロボット”を形にしていくのだと思っています。
アメリカ市場で勝負する──世界に通用するプロダクトと多国籍チームの挑戦
今後の展望について教えてください。
今、アメリカ市場での展開を本格化しています。現地法人も作って、ピッチイベントにも積極的に参加しています。アメリカは小売市場が世界最大ですし、新しい技術やサービスに対しての受容度も高い。特に「省人化」と「接客品質」の両立という点で、ロボットに対するニーズが日本以上に強く、ここで評価されれば世界市場への足がかりになると考えています。
グローバルで通用するかどうかが、鍵になるわけですね。
そうですね。海外で認められることは、プロダクトの本質的な価値を証明することでもありますし、同時にチームのモチベーションにもつながります。
一方で、プロダクトが“技術的にできた”だけでは意味がなくて、実際に導入されて“使われ続ける”ところまでいかないと、社会にインパクトは出せません。まさに今はそのフェーズにいて、導入先の現場でどう使ってもらえるか、どう運用設計するかを作り込んでいるところです。
組織としてはどのような進化を考えていますか?
社員は業務委託のメンバーも含めて30人強で、10カ国以上の国籍のメンバーがいます。リモート勤務のエンジニアも多く、国境もタイムゾーンも飛び越えて働いている感じですね。そのぶん、文化的な背景も多様なので、共通言語として「なぜこの会社で働くのか」というミッションへの共感がすごく重要になります。MUSEでは、「こういう社会をつくりたい」という強い思いを持った人たちが、自然と集まってきている実感があります。

ミッションに共感する仲間と、“人に光をあてる未来”をつくりたい
どんな価値観やスタンスを持った人に、MUSEの仲間になってほしいと考えていますか?
やっぱり、“タスク”ではなく“ミッション”として仕事を捉えられる人ですね。「社会的な意義があるからこそ、このプロダクトを世に出すんだ」と本気で思える人と働きたいです。MUSEでは、プロダクト単体ではなく“人にインスピレーションを届ける世界”をどう創っていくかがすごく重要なので、そのビジョンに共感してくれることが何より大切だと思っています。
今のフェーズでMUSEに参画する魅力は、どんなところでしょうか。
まさに今、プロダクトが世の中に広がり始める段階なので、「社会実装に関わっている」という実感が持てるのが一番の魅力だと思います。たとえばエンジニアはもちろん、カスタマーサクセスやBizDev、PdMなど、担当領域にとらわれず、ユーザーの声をもとにどんどん前に進める人にはすごくやりがいがある環境です。僕らがつくっているのは“人を輝かせるロボット”ですが、それを社会に届けていくには、最後はやっぱり人の力が必要なんですよね。ミッションに共感した仲間たちが、自然と自律的に動けるようなチームをつくっていきたいと思っています。
とっても素敵なお話をありがとうございました!!いつかこの挑戦の続きを聞かせてください。
編集後記
笠置さんの言葉からは、「技術」だけではなく「人」に軸を置くロボット開発という強い信念が伝わってきました。“人に光をあてるロボット”というビジョンは、単なるスローガンではなく、幼少期から続く原体験、キャリアの紆余曲折、現場での気づき、すべてを積み重ねて到達した答えなのだと感じました。
ロボットは、人を補完するだけの存在ではなく、人がもっと輝くための“余白”をつくる存在。そんな未来を信じ、実装しようとしているMUSEという挑戦の場所に、共感する人が集まることを心から願っています。

株式会社MUSE
https://www.muse-gr.com/
- 設立
- 2022年08月
《Mission》
ロボットで世界の人々にインスピレーションを。
《事業分野》
ロボティクス・小売・AI
《事業内容》
MUSEは、人の創造性やコミュニケーション能力といった本来の価値に光をあてる“共創型ロボット”を開発するスタートアップ。時間帯に応じて複数の業務を柔軟に担う「マルチユース型ロボット Armo(アルモ)」を軸に、国内外の小売現場への導入を進めている。単なる省人化ではなく、「人を輝かせる存在」としてロボットが社会に溶け込む未来を目指す。2024年には米国法人を設立し、グローバル展開にも注力している。
