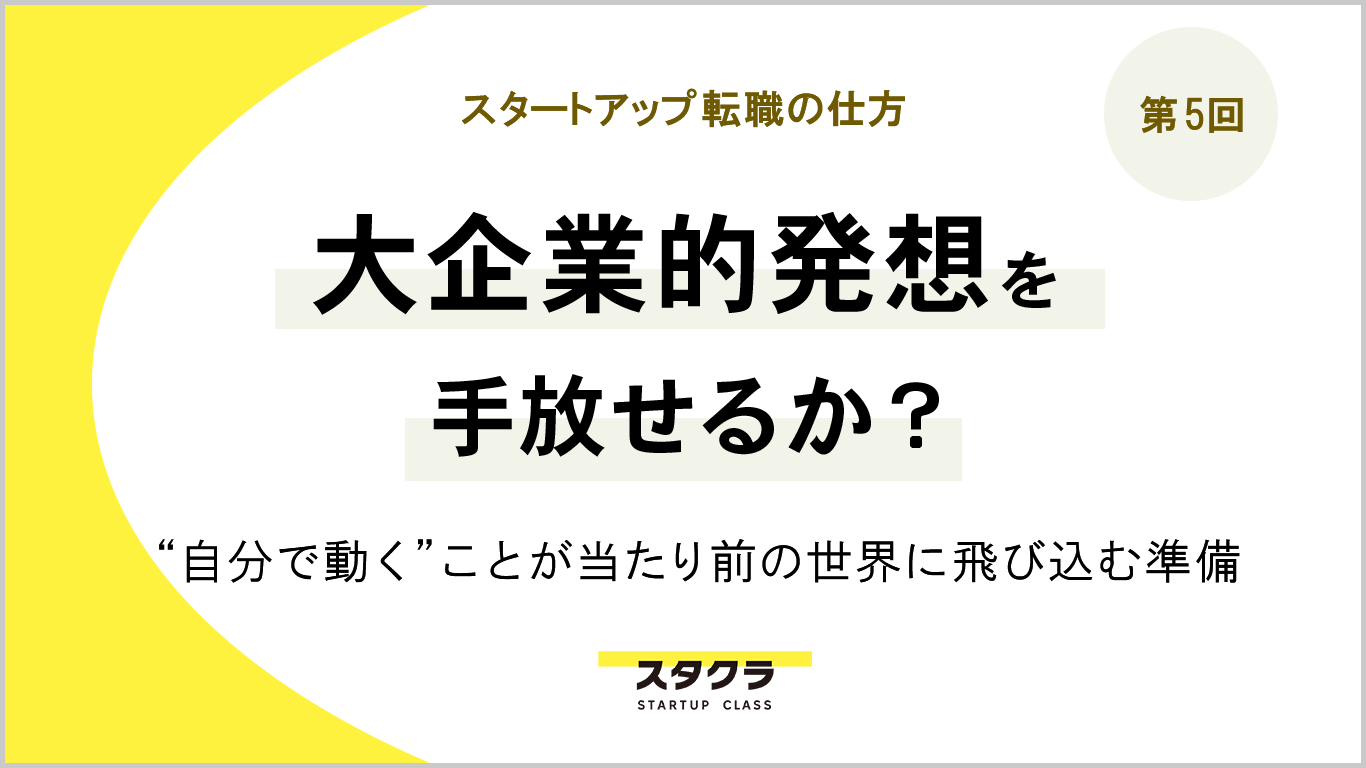
スタートアップ転職の仕方について、全24回の連載です。
自身のキャリアの考え方のヒントや、スタートアップへの挑戦の後押しに、ぜひご覧ください!
- 目次 -
はじめに:「前の会社ではこうだった」が通用しない世界
スタートアップに転職して最初に感じる違和感。
それは、「当たり前」が全く通用しないことです。
たとえば、こんな場面。
●「これって誰の仕事ですか?」→ 「誰もやってないから、やろうと思った人がやる」
● 稟議も報告書もなく、Slackで「これやります」で決定
● 数字の正確性より、まずは「仮説ベースで進める」ことが求められる
これらは一見、混沌に見えるかもしれません。
でもその奥には、「自分で考え、動き、つくっていく文化」があります。
スタートアップと大企業、“考え方のOS”が違う
ここでいう「大企業的発想」とは、以下のような思考習慣を指します。
| 大企業的発想 | スタートアップ的思考 |
|---|---|
| 正解を出す | 仮説で動く |
| 誰がやるかを確認 | 自分で拾う |
| 指示を待つ | 自ら定義する |
| ルールに従う | ルールをつくる |
大企業では、「仕組みの中でどう動くか」が重視されます。
一方、スタートアップでは、「仕組み自体をつくれる人」こそが求められるのです。
今までの成功体験を“手放す勇気”が、スタートアップでの第一歩となります。
自ら動く力=自走力が問われる
スタートアップで評価されるのは、肩書でも経験でもなく、“自走力”です。
自走力とは、単に「手を動かす人」ではありません。
● 状況を捉える力
● 優先順位を自分で決める力
● 課題を発見し、提案して形にする力
つまり、何もないところから“進める”力が問われるのです。
このとき、「指示待ち」や「確認前提」の思考は、大きな壁になります。
「自分の役割」を自分でつくる世界
大企業では、役割やKPIが明確に設定されています。
しかしスタートアップでは、役割が曖昧だったり、日々変わったりするのが当たり前です。
大切なのは、「何をやるべきか?」ではなく、
「何をやったら、チームが一歩前に進むか?」という問いを立てられること。
誰にも言われていないけれど「これ、今のフェーズに必要かも」と思ったら、
まずは“動いてみる”。そこから、新しい価値が生まれるのです。
成功体験より、柔軟さが武器になる
大企業での経験がある人ほど、
「こうすれば上手くいく」という“型”を持っているものです。
でも、スタートアップではその型が通用しないことが多い。
● チーム人数も少ない
● 市場も曖昧
● 事業モデルもピボットする可能性あり
だからこそ、「経験に頼る」よりも、“柔軟に試す”マインドの方が価値を生むのです。
「知っていること」よりも、「変われること」が、あなたの強さになります。
「正解がない」ことを、楽しめるか?
正解がない。答えがない。やり方も決まっていない。
それを“怖い”と思うか、“面白い”と思うか。
この感覚こそが、スタートアップに向いているかどうかの一つの指標です。
スタートアップは、自分で問いを立て、答えを探し、周囲を巻き込んで形にしていく場所。
つまり、ルールに従うのではなく、ルールを提案する人が活躍できる環境です。
おわりに:自分の“OS”をアップデートするということ
「大企業的発想を手放す」とは、
これまでの経験を捨てることではありません。
「経験の使い方」を変えることです。
指示通りに動いて成果を出す、から
自分で意思決定し、環境ごと変えていく、へ
これが、スタートアップ転職の本質的な変化です。
そしてそれは、新しいキャリアの可能性を切り開く、最も刺激的な変化でもあります。
次回は、「染み出し」というキャリア戦略についてお届けします。
今あるスキルをどうスタートアップに“にじませる”か。お楽しみにお待ちください。
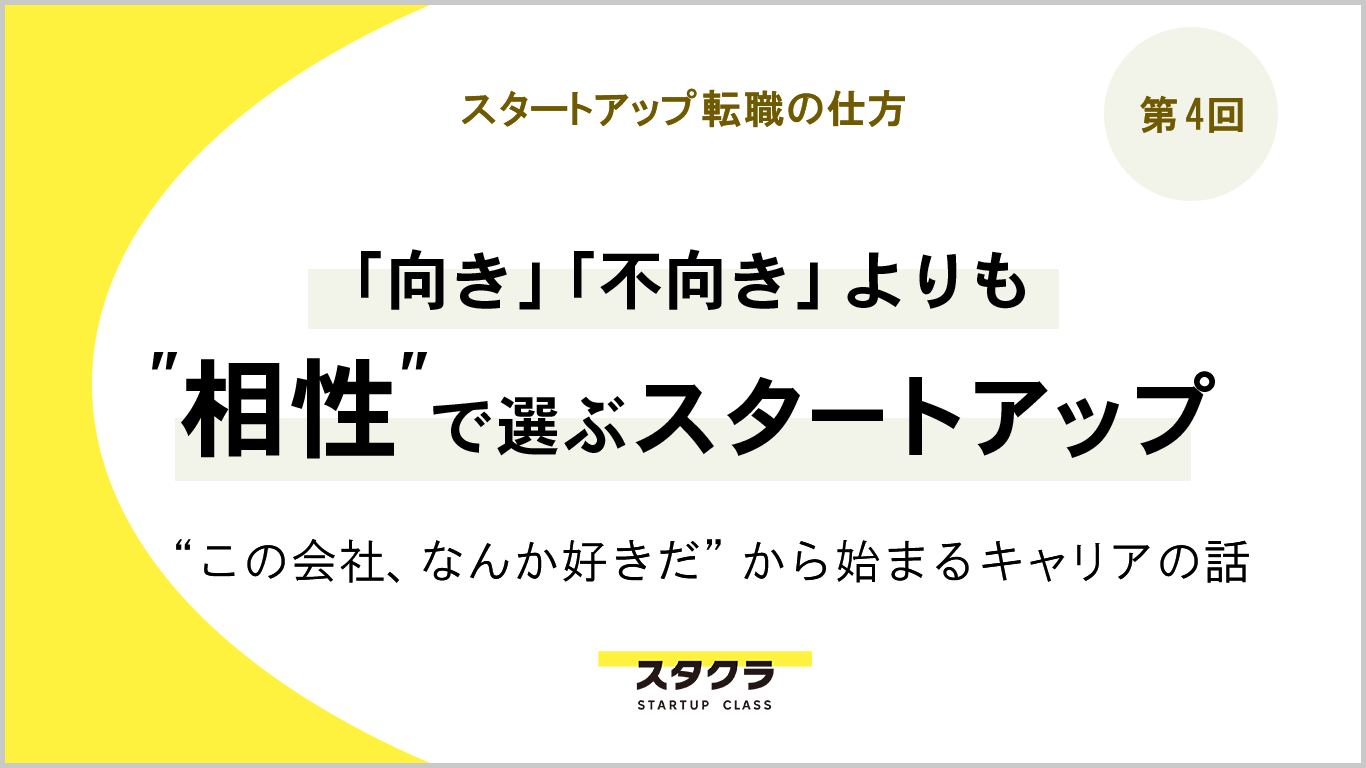
#4.「向き・不向き」よりも“相性”で選ぶスタートアップ
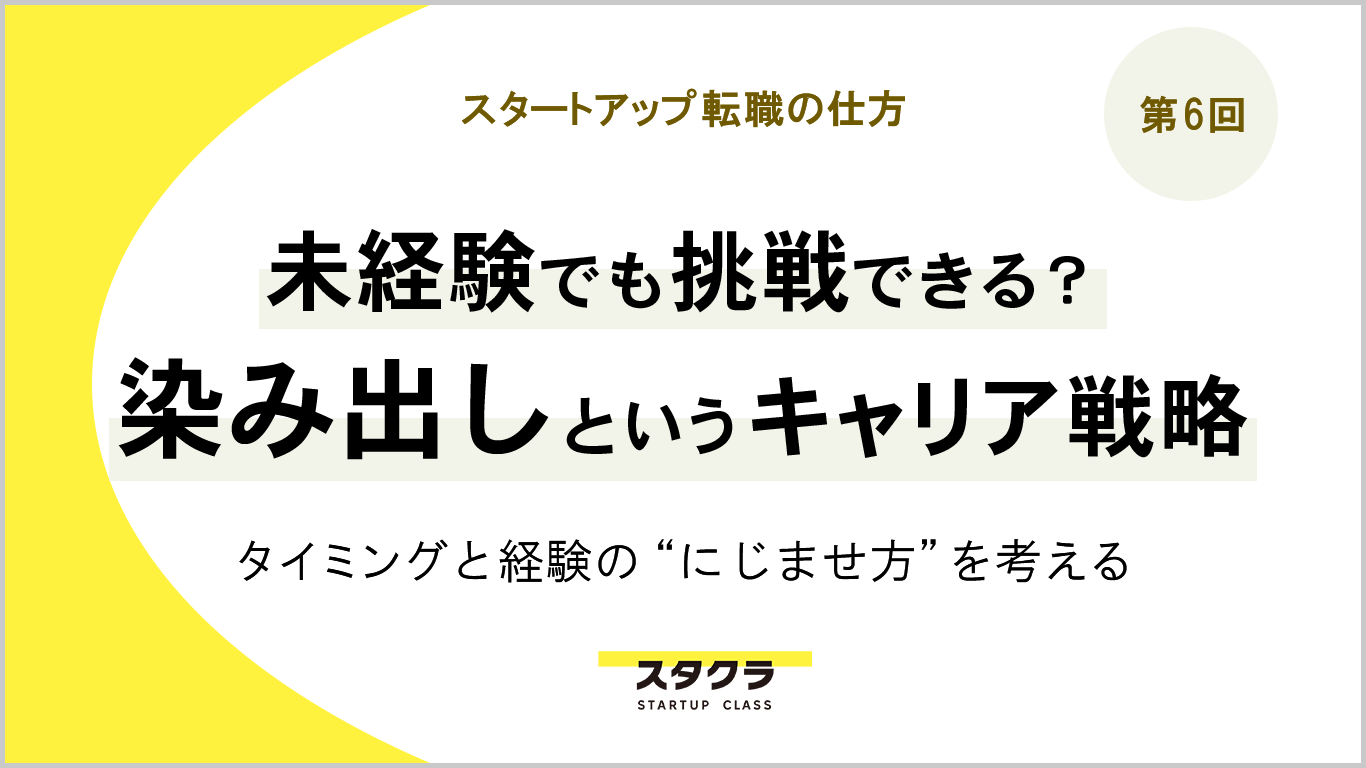
#6.未経験でも挑戦できる?「染み出し」というキャリア戦略
