
CO₂排出量の削減が叫ばれる中、注目される“直接空気回収(DAC)”の最前線で技術開発に取り組むPlanet Savers。2024年に入社した大木氏は、長年日系、外資系の化学メーカーでキャリアを積み重ねてきたサイエンティストだ。
安定した環境から、あえてスタートアップという不確実性の高い環境へ。入社の決め手となったのは、「この業界に今から関われることが、自分にとってのチャンスだった」という確信だった。
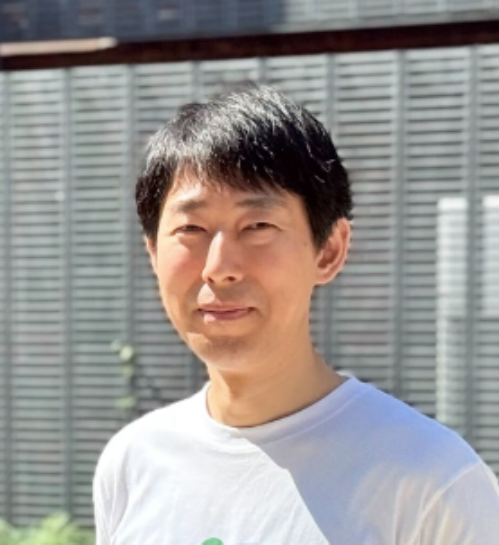
リードサイエンティスト
大木 知則氏
新卒で日系の化学メーカーで研究開発に従事し、その後、外資系企業(DuPont, Johnson Mattheyなど)で、主に電子機器・自動車向けの導電性ペースト、触媒などの開発に従事。原材料・製品開発から量産立ち上げ、品質トラブル、顧客対応と製造業の川上から川下まで幅広く経験。これらの経験・知識を活かして日本のモノづくりを軸にしたスタートアップに貢献したいという思いから2024年にPlanet Saversに入社。

Planet Savers株式会社
https://planetsavers.earth/
<Mission>
気候変動を食い止め、次世代に美しい地球を残す
<事業内容>
2050年に1ギガトンのCO₂を回収し、100年後も美しい地球を守るための、実用レベルのDAC技術の開発・提供
- 目次 -
キャリアに正解はない。20年の製造業キャリアからスタートアップへ
まずはこれまでのご経歴を教えてください。
2003年に東洋インキ製造(現artience)という会社に入社し、そこでは印刷インキに関する研究開発に携わりました。以降は一貫して「化学」と「材料」を軸に、複数の企業で開発職を続けています。
エレクトロニクスや自動車業界向けの金属やセラミックスのペースト、触媒などの開発を担当しながら、プロジェクトリーダーや開発マネージャーも経験してきました。ずっと“ものづくりの最前線”で研究開発に向き合ってきたという感じですね。
安定した大手・外資企業を経て、なぜスタートアップという選択肢を?
キャリアの前半は大手企業に勤めていたのですが3社目の会社が従業員60名程度の小さな会社で、そこでは開発だけではなく、製造、品質保証まで幅広い業務に裁量を持った立場で関わることができました。この会社での経験が自信になり、大手企業より中小もしくはスタートアップのような会社の方が自分の力を発揮できるのではないかと思うようになりました。
スタートアップに初めて飛び込んだのが、リチウムイオン電池の部材を開発する素材スタートアップ。期待通り最先端技術に関わることができ、働く環境も合っていました。製品開発、中量産の立ち上げに成功、有償サンプルでしたが売上が立ち始めてこれからというタイミングで会社の資金繰り悪化による給与未払いが発生して…1年弱でやむなく退職することになりました。
そのタイミングで、池上さん(Planet Savers代表)からスタクラを通して声をかけてもらいました。最初は「転職の意思はないです」と前置きをしていたんですが(笑)、面談をして話を聞いていく中で、「この技術、この会社、このタイミング」に強く惹かれていったんです。
どういったところに魅力を感じたのでしょうか?
やはり創業初期のフェーズから関われるという点は大きかったですね。前職のスタートアップでは開発フェーズがほぼ終わっていて、設計や仕様を根本から変える余地が少なかった。
でもPlanet Saversでは、まだ正社員が数名というタイミングでしたし、技術も組織も「つくるところから入れる」環境。そこにワクワクしました。

CO₂回収の最前線。「地球を救う装置をつくっている」実感がある
今はどんな業務を担当されているのですか?
CO₂吸着材であるゼオライトの合成・成型・評価・量産化の一連の開発に関わっています。私たちPlanet Saversの強みの一つは、ゼオライトを自社で合成できるという点です。これは世界のDACメーカーでも数社しか持っていない技術です。
研究室レベルで終わらせるのではなく、それを装置に組み込める成型体に加工し、評価・量産まで持っていく。その橋渡しを担うような役割です。私はこれまで20年以上、製造現場に近い研究開発をやってきたので、そこでの経験が「製品を世に生み出すまでが開発」というミッションに生かされていると感じています。
今後注力していく取り組みはありますか?
今まさに、東京都の実証プロジェクト(東京ベイeSGプロジェクトの先行プロジェクト)に採択されていて、東京湾岸の臨界エリアにDAC装置を設置する予定です。そこでは、実際に大気中からCO₂を回収する工程をリアルに動かすので、絶対に失敗できない。
チーム全員で力を合わせて進めていて、個人としても、今はそこに全力で集中しています。
小さな組織だからこその魅力。心理的安全性と裁量
スタートアップに転職して、何かギャップはありましたか?
良い意味でのギャップとしては、研究開発に使える予算がしっかりあることですね。前職のスタートアップでは資金繰りが厳しく、研究どころではないことも多かったので…。Planet Saversは補助金や助成金の活用も含めて、研究に集中できる環境が整っていて、とてもありがたいです。
一方で、人手が少ないので何でも自分でやる必要があるというのは、やはり大変な面もありますね。特に化学系・製造業を経験したサイエンティストはまだまだ少なくて、私のようなバックグラウンドを持つ人がもっと来てくれたらいいのに、という思いはあります。

「何にワクワクするか」で選んでいい。スタートアップ転職を迷う人へ
スタクラをご利用いただいたきっかけを教えてください
最初は登録だけしてみようと思いました。でも企業情報を眺めているうちに、スタートアップという世界に少しずつ興味が湧いていきました。実際、紹介してもらった企業の面談を受けたり、情報に触れたりする中で、「いつかはこういう場所で働いてみたい」と思うようになっていったんです。
だから、少しでも関心があるなら登録して、いろんな会社に触れてみることが大事だと思います。選択肢を知るだけでも、視野は大きく広がります!
どんな方に、今後この会社に来てほしいですか?
特に日本のサイエンティストの方々には、もっとスタートアップに飛び込んでほしいと伝えたい気持ちがあります。研究を続けることももちろん素晴らしいけれど、「地球温暖化を技術で止める」というテーマに対して、自分の知識やスキルで本気でチャレンジしてみたいなら、こういう場所があるよ、と伝えたいです。
特にはじめてスタートアップへ転職する際は、最後の一歩で踏みとどまってしまう方も多いです。不安もわかりますし安定を手放すのは勇気がいりますが、今の経験はきっと次に生きるし、何よりここでの経験自体が唯一無二のものになると思っています。
編集後記
外資系企業でキャリアを積み、安定や専門性を手にしていた大木さんが、スタートアップという挑戦の場に自ら飛び込んだ背景には、「この技術は、世界が必要としている」という確信があった。
社会課題に向き合う技術者の姿からは、立場や年齢に関係なく、挑戦には意味があるというメッセージが強く伝わってくる。
このインタビューが、いま一歩を迷っている誰かの背中を、ほんの少しでも押せたなら嬉しい。

Planet Savers株式会社
https://planetsavers.earth/
<Mission>
気候変動を食い止め、次世代に美しい地球を残す
<事業内容>
2050年に1ギガトンのCO₂を回収し、100年後も美しい地球を守るための、実用レベルのDAC技術の開発・提供
