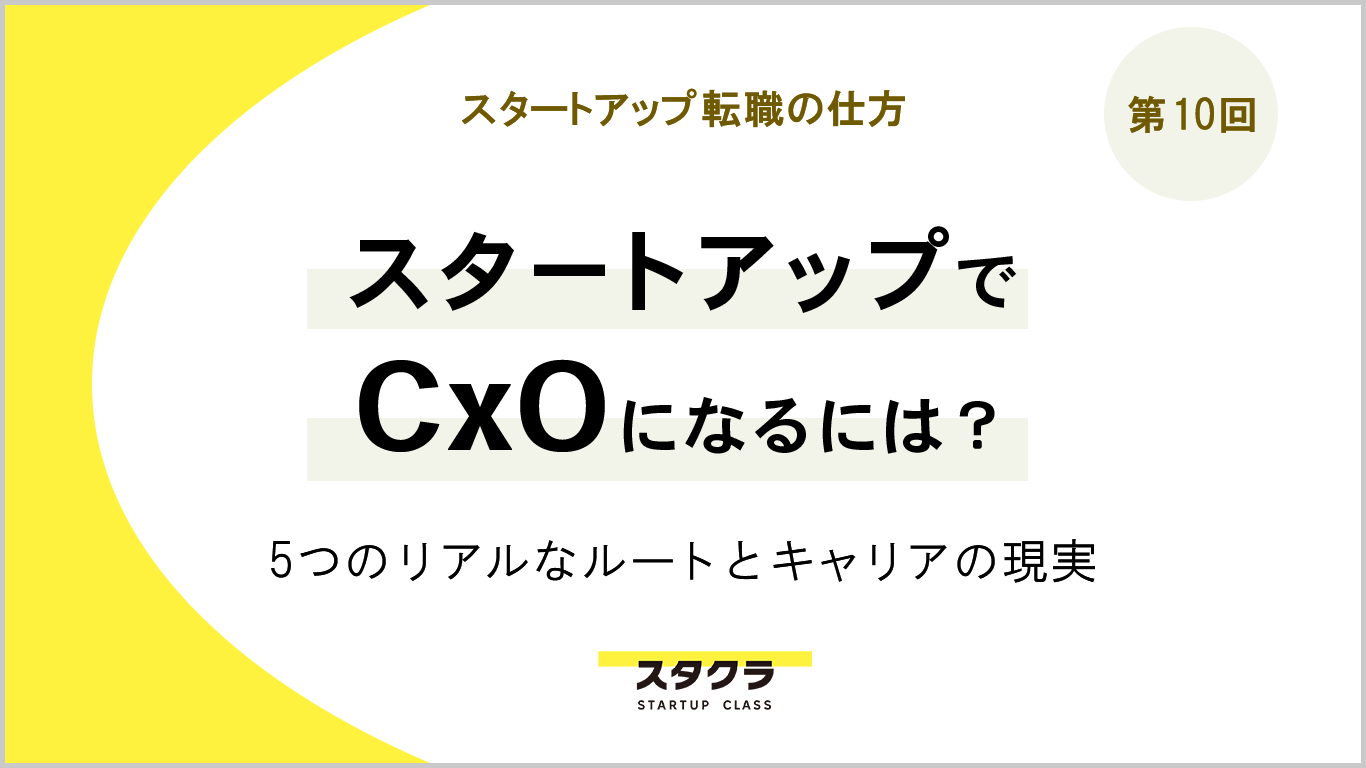
スタートアップ転職の仕方について、全24回の連載です。
自身のキャリアの考え方のヒントや、スタートアップへの挑戦の後押しに、ぜひご覧ください!
- 目次 -
はじめに:「CxOになりたい」という想いに必要なこと
「スタートアップでCxOになりたい」という声は、今や珍しくありません。
経営に携わりたい、企業の中核を担いたい——そんな想いは、特別な野心ではなく、自然なキャリアの一歩になりつつあります。
ただし、CxOになるには「想い」だけでは不十分です。
経営視点で考える力と、経営課題を自ら解決する力の両方が求められます。
現実的に、スタートアップでのCxOは、CFO(最高財務責任者)、COO(最高執行責任者)、CTO(最高技術責任者)のいずれかが中心です。
ですが、共通して問われるのは、単なるスキルではなく、「経営のWHYを解決する力」を持っているかどうかです。
そして、それぞれに就くには、適したルートと準備が必要です。
“いつかはCxOになりたい”——そんな想いがある方は、ぜひ次章を参考に、今から自分なりの第一歩を考えてみてください。
①創業メンバーとして参画(フェーズ:シード/アーリー)
最もダイレクトなルートが、「創業メンバー」としてCxOの座に就くことです。
社長の知人であったり、立ち上げ時から関わったりすることで、ポジションが空いている状態で参画できるケースです。
このルートの特徴は、「実績がなくてもチャンスがある」という点。
一方で、会社の成長とともに後から入ってきたプロ人材にリプレイスされるリスクも抱えています。
覚悟と成長の意思がある人には、夢のあるチャレンジです。
②拡大ステージでCxO参画(フェーズ:ミドル〜レーター)
ある程度プロダクトや事業が立ち上がり、「さあ、ここから拡大だ!」というタイミングでCxOを求められるケースです。
この段階では、実務とマネジメントの両面での即戦力性が問われます。
特に「プレーイングマネジャー」としての器用さが重宝されます。
注意したいのは、「肩書き」よりも「現場スキル」が見られる点。
たとえば、CFOでも「決算が回せない」「現場の数字を見られない」となると、信頼を失うこともあります。
③経営確立フェーズでCxO参画(フェーズ:レーター〜グロース)
このパターンが最もハードルが高いと言われる理由は、
すでにステークホルダーや株主が多く、あとから加わる人への“納得感”が非常に求められるからです。
・ハイスペックな経歴や実績
・即効性のある成果
こうした「一目でわかる強み」がないと、オファーが出ることすら難しいのが実情です。
④社員として入り、のちにCxO昇格
現実的かつ地に足のついたルートが、「一社員として入り、社内昇格でCxOになる」という道です。
もちろん、チャンスが巡ってくるには「信頼」「実績」「タイミング」の3つがそろう必要があります。
とはいえ、最初からCxOを目指さなくても、地道に信頼を積み重ねていけば道は開ける可能があります。
⑤経験を積んでからCxO転職
最もおすすめするのが、「1社目で実績をつくり、2社目でCxOになる」というルート。
たとえば、「レーター期」「グロース期」の知名度があるスタートアップで実務経験を積んだのち、
「アーリー〜ミドル期」の会社でCxOとしてジョインする──という流れです。
このパターンでは、
・実績=信用資産
・人脈=推薦の力
・失敗経験=成長の証
として効いてきます。スタートアップ村の中で「あの人、良い仕事してたよね」と評価されることが、次のCxOポジションへのパスポートになります。
「いきなりCxO」をおすすめしない理由
もちろん、タイミングや縁があれば、いきなりCxOになることも可能です。
でも、正直いきなりCxOを目指すことは、おすすめしません。
・経営視点で物事を考えるマインドがあるか
・企業の成長課題に対して、自らアプローチし、達成できる実行力があるか
この両方が揃ってはじめて、CxOというポジションが現実的となってきます。
・社内調整力がない
・経営課題を知らない
・プレーイングスキルが不足している
こういったギャップを乗り越えるには、どうしても経験と信頼が必要になります。
1社目のスタートアップ転職ではCxOにこだわらずに、しっかりとスタートアップで経験を積んで他社から声がかかる状況にしておくほうが、ソフトランディングできて失敗リスクが少ないのです。
おわりに:「CxO」はゴールではなく、スタート地点
CxOになることは、あくまで通過点です。
本当に問われるのは、「CxOとして、何を成し遂げるか」。
だからこそ、“CxOになること”にこだわりすぎず、まずは“信頼される仕事”を一つひとつ積み重ねていくことが、いちばんの近道になるのではないでしょうか。
CxOを目指す道にも、フェーズ選びにも、「その会社がどこを目指しているか」という視点は欠かせません。
では、そもそも「これから伸びるスタートアップ」って、どうやって見極めればいいのでしょうか?
次回は、社会課題とのつながりやSDGsとの関連性をヒントに、今後の有望スタートアップの見つけ方を考えていきます。
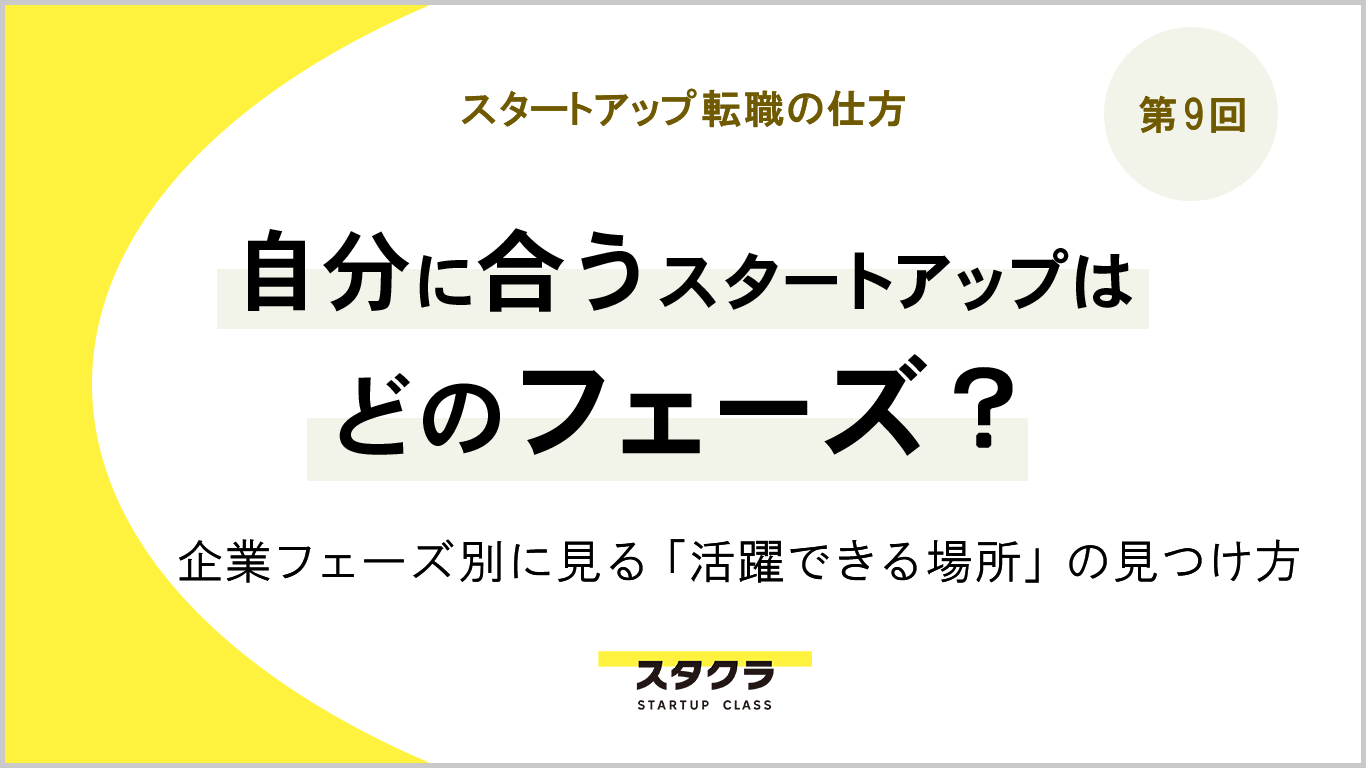
#9.自分に合うスタートアップはどのフェーズ?
