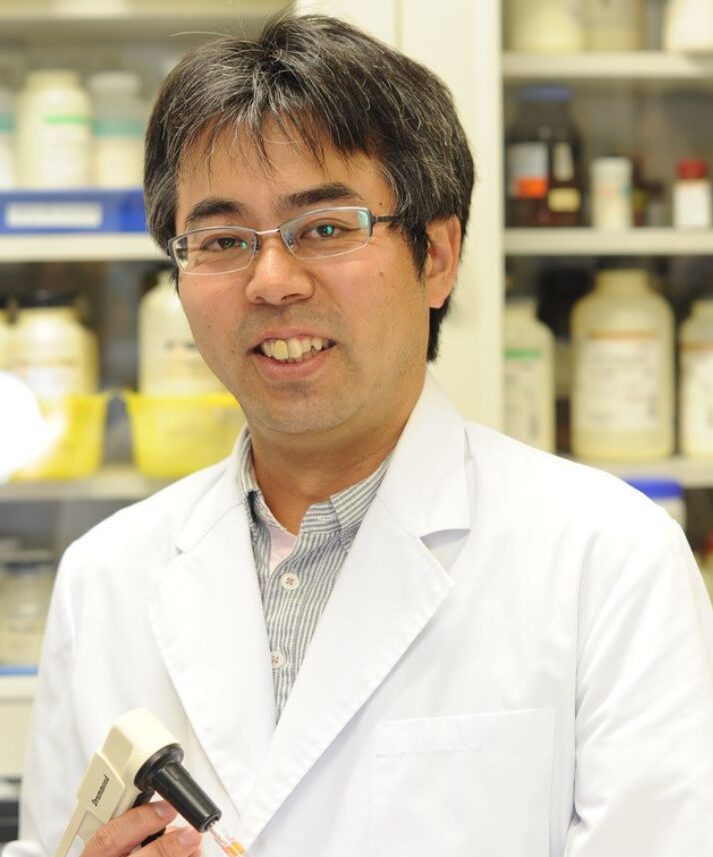
がんや精神疾患などの分野で注目を集める「エピジェネティクス」。その革新的な研究が、いま眼科疾患の新しい治療法としても注目されています。福井大学の沖昌也教授は、糖尿病網膜症による失明リスクの低減を目指し、点眼薬の開発に挑んでいます。
国の支援を受けた事業化プロジェクト「TeSH GAPファンド」を通じて、非侵襲で虚血を改善する点眼薬の実現に向けて動き出した研究者の熱い想いと挑戦に迫ります。
※TeSH GAPファンドプログラム:大学等の研究機関における優れた研究成果の事業化を目的とした、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の支援プログラム
-e1753233402592.png)
学術研究院工学系部門 生物応用化学講座 教授
沖 昌也氏
福井県出身。九州大学大学院医学系研究科で博士号を取得後、米国立衛生研究所(NIH)に留学。長崎大学医学部助手、理化学研究所研究員を得て、2006年から福井大学工学部に准教授として着任。2009年から3年間JSTさきがけの研究員を兼任し、2018年から福井大学大学院工学研究科教授に就任し、現在に至る。同2018年から福井大学ライフセンターイノベーションセンター副センター長、2023年からは日本学術会議連携会員を兼任。専門は分子生物学。現在、2年後のスタートアップを目指し奮闘中。
生物化学研究室
https://sites.google.com/view/biochem-hp

福井大学
https://www.u-fukui.ac.jp/
≪大学理念≫
「格致(かくち)によりて 人と社会の未来を拓(ひら)く」
近代福井の礎(いしずえ)を築いた松平春嶽公の揮毫による本学所有の「格致」の額面は、同人の歴史的功績を考えれば本学の宝であると言えます。「格致」とは「物事の道理や本質を深く追求し、理解して、知識や学問を深め得ること」という意味です。
本学学生にとっては、学びと人格育成に際し、また教職員においては、研究・教育・社会貢献等で自らの指針となる語句です。我々は、この語句を旨とし、県内より世界に至る様々な地域において、そこに集う人、ならびに社会の未来を拓くことに主体的にかかわり、貢献することを目指します。
糖尿病網膜症点眼薬の開発でスタートアップ立ち上げを目指す
ご経歴や、現在の研究をするに至った背景について教えて下さい。
福井県生まれで、富山大学大学院で化学生物工学を学んだ後、九州大学大学院医学系研究科で分子生命科学を専攻し、1999年に博士号を取得しました。
米国立衛生研究所(NIH)への留学や、長崎大学医学部、理化学研究所での研究を経て、2006年に福井大学に准教授として着任しました。2018年からは教授を務めています。JST「さきがけ」研究員や、日本学術会議の連携会員も歴任し、現在は長年のエピジェネティクス研究をもとに、創薬スタートアップの立ち上げを目指しています。
現在取り組んでいるのは、「虚血領域にアプローチする非侵襲糖尿病網膜症点眼薬の開発」です。糖尿病網膜症になると、目に“虚血領域”と呼ばれる、血流がうまく流れない箇所ができ、そこに異常な血管が発生することがあります。最終的には失明につながるため、手術など何らかの治療が必要です。
現在の標準治療は異常な血管の増殖を抑える「抗VEGF阻害薬」の注射ですが、この薬では異常血管を減少させることはできても、虚血そのものを治すことはできません。そのため、繰り返し注射を受ける必要があり、患者への負担が大きく、費用も高額であることが問題になっています。
そこで私たちが開発したのが「Z3-5」という低分子化合物です。マウスでの研究を重ねた結果、虚血領域を改善するマスター因子を同定することに成功し、虚血そのものを治すことができる画期的な化合物を作ることができました。
開発のベースには、私が長年取り組んできたエピジェネティクスの基礎研究があります。エピジェネティクス(Epigenetics)とは、後天的に遺伝子の使い方が制御される仕組みのことで、いま創薬の分野で注目を集めています。
人間の細胞は、一つの受精卵からDNAを複製してできているので、個々の細胞が持つDNAは同じです。ただし、遺伝子の使い方は脳や心臓、肺や腸といった細胞ごとに異なる働きを持つよう制御されています。つまり、同じDNAを持っている細胞でも遺伝子の使い方が変わることで、異なる形・性質の細胞に変化するのです。
病気も同じで、後天性疾患の場合、ある時点で遺伝子の使い方が変わることで発症します。そうした病気になる“分岐点”を見つけて投薬し、正常な方向に導くことで病気を治すというのが、私が取り組んでいる研究です。「図書館の書架で間違った分類に入ってしまっている本を、正しい分類に戻してあげる」というイメージがわかりやすいかと思います。
高齢化も進んでいる中で市場は非常に大きく、どんどん広がっています。現在はGLP毒性試験(※)の段階で、今年1年くらいかけて点眼薬としての実現可能性を検証し、開発を進める計画です。
※JSTさきがけ研究員:国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が、将来有望な若手研究者を支援する「さきがけ」プログラムの研究員のこと
※GLP毒性試験:医薬品の安全性を調べるために、動物などを用いて行われる非臨床試験のこと。Good Laboratory Practiceの略

ヒトは約2万3000個の遺伝子を持つ。生活習慣の変化が遺伝子のON/OFFを切り替え、病気のきっかけとなることもある。

福井大学
https://www.u-fukui.ac.jp/
≪大学理念≫
「格致(かくち)によりて 人と社会の未来を拓(ひら)く」
近代福井の礎(いしずえ)を築いた松平春嶽公の揮毫による本学所有の「格致」の額面は、同人の歴史的功績を考えれば本学の宝であると言えます。「格致」とは「物事の道理や本質を深く追求し、理解して、知識や学問を深め得ること」という意味です。
本学学生にとっては、学びと人格育成に際し、また教職員においては、研究・教育・社会貢献等で自らの指針となる語句です。我々は、この語句を旨とし、県内より世界に至る様々な地域において、そこに集う人、ならびに社会の未来を拓くことに主体的にかかわり、貢献することを目指します。
