
九州大学の100%子会社として2024年4月に設立された九大OIP株式会社は、九州大学の産学官連携を先導する組織。OIPはオープンイノベーションプラットフォームの略で、大学と産業界の接点として、両者の橋渡しを通じたエコシステムの構築をめざしています。
九州大学の教授で、九大OIP株式会社の執行役員兼サイエンスドリブンチームディレクターである古橋寛史氏、福岡市役所から九大OIP株式会社に出向している高増健⼀氏のお2人に、九大発スタートアップの強みや課題などを伺いました。特許で利益を得ることを悪だと考えていた研究者時代を経てライセンス化を推進する側に転身した古橋氏、スタートアップ支援部署に異動して「心躍る仕事に出合えた」という高増氏のお話からは、研究者を産業界や社会とつなぐ橋渡し業務の重要性、スタートアップ支援業務のやりがいや喜びが伝わってきました。

執行役員 兼サイエンスドリブンチームディレクター
古橋 寛史氏
九大OIP株式会社 執行役員。理学博士。国立遺伝学研究所、米・エモリー大学での研究活動を経て、東北大学薬学研究科の教員としてライフサイエンス領域における教育と研究に従事。その後、 関西TLO株式会社(現 株式会社TLO京都)で、大学知財の権利強化、ライセンス活動やスタートアップ創出支援を推進。2023年からは九州大学 学術研究・産学官連携本部の教授、そして九大OIP株式会社の執行役員を兼務する。
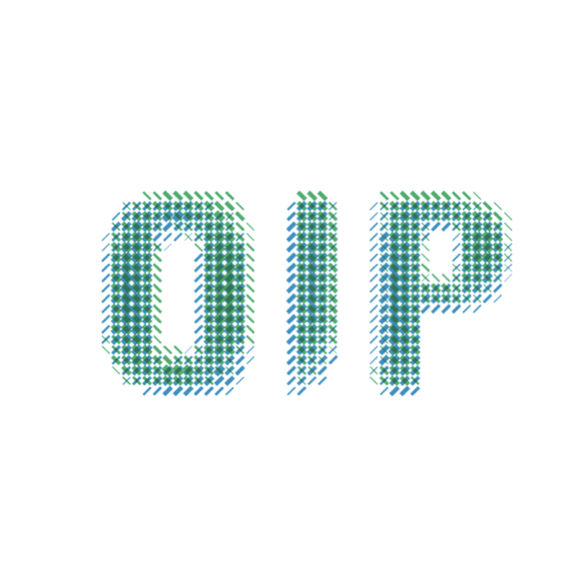
九大OIP株式会社
https://ku-oip.co.jp/
≪MISSION≫
九大OIPは、九州大学の産学官連携を
先導する組織である。
われわれは、大学の教育・研究の向上に資する
産学官連携活動を支援する。
≪VISION≫
九大OIPは大学と社会とのインターフェースとして、
九州大学が起点となるエコシステムの構築を目指す。
≪事業概要≫
① 成果活用促進事業(共同・委託研究等の企画・あっせん)
② 研究成果活用事業(コンサルティング及び研修・講習に関する業務)
・大学等の研究成果を実用化するために必要な共同・受託研究等を企画・あっせんする業務
・共同・受託研究等プロジェクトのマネジメント業務
・大学等の研究成果を活用したコンサルティング、研修・講習等業務
・大学等の研究成果を産業技術として企業に移転する業務
・大学等の研究成果を活用したベンチャー企業の創出・育成支援 など

サイエンスドリブンベンチャーサポートコーディネーター
高増 健⼀氏
九大 OIP 株式会社 サイエンスドリブンベンチャーサポートコーディネーター
福岡市役所から出向。市役所入庁後は、市営住宅の建替事業や生活保護業務、青果
市場の統合移転整備事業等を担当した後、スタートアップ支援施設「Fukuoka
Growth Next」の立ち上げから運営を4年間実施し、福岡市産学連携交流センター
(FiaS)の担当として大学発スタートアップ支援を経て、2022 年度より九州大学
オープンイノベーションプラットフォームに出向。
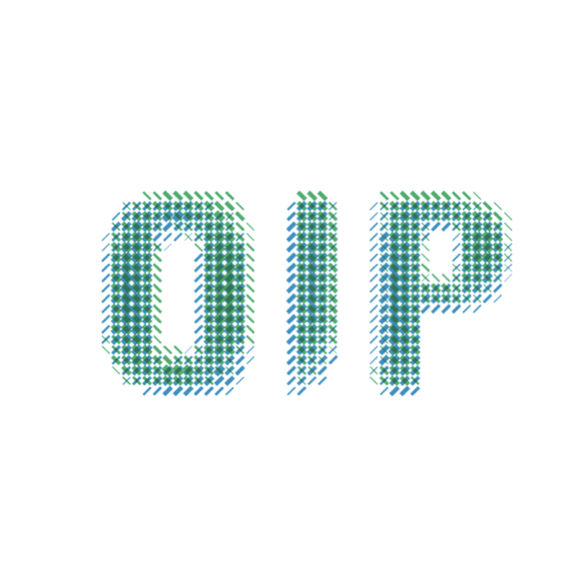
九大OIP株式会社
https://ku-oip.co.jp/
≪MISSION≫
九大OIPは、九州大学の産学官連携を
先導する組織である。
われわれは、大学の教育・研究の向上に資する
産学官連携活動を支援する。
≪VISION≫
九大OIPは大学と社会とのインターフェースとして、
九州大学が起点となるエコシステムの構築を目指す。
≪事業概要≫
① 成果活用促進事業(共同・委託研究等の企画・あっせん)
② 研究成果活用事業(コンサルティング及び研修・講習に関する業務)
・大学等の研究成果を実用化するために必要な共同・受託研究等を企画・あっせんする業務
・共同・受託研究等プロジェクトのマネジメント業務
・大学等の研究成果を活用したコンサルティング、研修・講習等業務
・大学等の研究成果を産業技術として企業に移転する業務
・大学等の研究成果を活用したベンチャー企業の創出・育成支援 など
- 目次 -
九大で学んだ高度専門人材が、自ら雇用と産業を創出するまちづくり
九大OIP株式会社のミッションや主な取り組み、そして実績について教えていただけますでしょうか。
九州大学はビジョン2030として、九州大学の「総合知で社会変革を牽引する」という将来像を掲げています。九大OIPはそのもとで、産学連携活動を牽引して九州大学の教育・研究のさらなる発展を支えていくことをミッションとしています。
九州大学で育った高度専門人材、具体的には大学院の修士・博士過程を修了した方々などがどんどん九州から出て行ってしまっています。
そこで我々は、九州大学の周辺で彼らが自分たちで新しく雇用をつくり出し、そこに産業が生まれるまちづくりを、ひとつのゴールとして掲げています。
これは福岡市、福岡県など自治体とも共有しています。実績はこれからですが、2024年度時点で九大発スタートアップの数は170社以上あり、そのうち大学研究成果をベースにした企業が90社程あります。
福岡市はどんなスタートアップ支援を行っているのでしょうか。
行政ができるのは、民間の動きを制限せず、スタートアップが起業しやすい環境を整えることです。
福岡市は、誰でもチャレンジしていいという機運を醸成するため、2012年にスタートアップ都市宣言を行いました。まずはプレイヤーを増やさないといけません。そして2014年にスタートアップカフェを設けました。どこの自治体でも起業の相談や手続きは商工会議所などで行うと思いますが、堅苦しい雰囲気になりがちです。
そこで気軽に弁護士や社労士といった専門家に相談してもらえるよう、朝から夜まで開いていて仕事帰りにも立ち寄れる環境を整えました。それを進化させたのが、コミュニティ拠点でありインキベーション施設として入居もできるFGN(Fukuoka Growth Next)です。
「悪」から「武器」へ、特許についての認識を改めたことが転機に
お2人それぞれの略歴と九大OIPでスタートアップ支援に携わるようになった背景についても簡単に教えていただけますでしょうか。
私は十数年前まで大学の研究者で、東北大学で薬学の教員としてバイオ系の研究をしていました。そのときファカルティ・ディベロップメント(教員研修)があり、産学連携や知的財産権をベースにした研究成果による社会貢献について学びました。当時の私は知識不足から特許について誤解していて、大学の研究成果で儲けようとするなんて悪だとすら思っていました。
でもその研修で、研究成果を社会課題の解決の役立てるためには権利化して事業者が適切に活用できるようにしないといけないと知り、考えを改めました。
特許はひとつの排他権であり、大学研究成果をビジネスにして社会に役立てるための強力な武器になること、特許がなければ誰もが使えてしまうため、ビジネスにならず、結果的に研究成果による社会貢献が限られてしまう場合もあることを聞き、特許ってそういうことなのかと初めて知りました。そして、研究成果の社会実装を手伝う仕事に関心を持ち、この世界に飛び込みました。
九州に来る前までは、関西で大学の特許管理や技術移転などを支援する会社で働いていました。その時に一緒に仕事をさせていただいた現 九州大学副理事の大西先生から九州大学の研究シーズの魅力や産官学連携に対する前向きさ、みんなで社会実装にチャレンジする雰囲気など含め、「九州はすごくいいぞ」とお聞きしていました。実際、九州には出張で何度か来ていて、福岡の雰囲気は本当に良いなと思っていました。
スタートアップ支援部署への異動で、心躍る仕事に出合えた
私は3年ぐらい前に福岡市役所から出向してきました。それまでは市の職員として、生活保護業務や市営住宅の建替事業といった仕事をやってきました。福岡市は2012年にスタートアップ支援を打ち出し、私は2016年にスタートアップ支援の部署に異動しました。
それまでは、役所の業務は市民からクレームを言われるし、あまり前向きに取り組める仕事はないと思っていました。でもスタートアップ支援業務には、新しいことを生み出して社会を活性化し、人を元気にする力がありました。暗いニュースばかりで閉塞感ただよう中、役所でもこんなことができるのかと、心躍る仕事に出合えた感覚がありました。
新しいことの連続で右も左もわからない状態でしたが、FGNの立ち上げと運営に3~4年携わり、スタートアップの現状や地域の状況が見えてきました。次世代有機EL材料の開発に取り組むKyuluxなど面白い九大発スタートアップが出てきていることは知っていましたが、市役所やFGNのある天神と九大がある西区は少し離れていますし、福岡市はずっとITに力を入れていたこともあり、情報をあまり共有できていませんでした。スタートアップ支援を大学と一体的に進めなければと感じました。
そんなときに産学連携の部署に異動になり、福岡市産官学連携交流センターの担当として大学発スタートアップ支援に2年間関わりました。そこで改めて、市は大学と同じ方向を向いて進むべきだと考えるようになりました。自治体は政権によって方針も変わる面があるので、情報をしっかり共有するために私が出向して一緒にやっているというわけです。

PARKS:九州大学及び九州工業大学が主幹機関となっている九州・沖縄エリアの大学発スタートアップエコシステム
「Platform for All Regions of Kyushu & Okinawa for Startup-ecosystem」のイニシャルからPARKS。
論文のインパクトや注目度、年間100件以上の発明届が示す高い学術レベル
国内の他の地域や大学との違い、世界的に見た場合を考えると、どんなところが九大発ディープテックの特徴でしょうか。
例えば、水素、脱炭素など、環境・エネルギー関連技術、農業×プラズマ科学といった、一次産業とディープテックを掛け合わせたものなどが盛んですね。そして宇宙関連事業。いろいろバリューチェーンができつつありますし、高精細小型レーダー衛星の開発を行うQPS研究所(東証グロース上場)も九大発のスタートアップです。
九州大学病院と連携した医療分野のスタートアップも注目されています。最近は半導体分野も益々ホットです。台湾の半導体メーカーTSMCの工場が熊本に建設され、九州の産業界も半導体のサプライチェーン構築推進に取り組んでいます。そんな中、九州大学もキープレイヤーとして期待されていると思います。
論文のインパクトや注目度を統計解析してみると、学術の観点からも九州大学のレベルは相当高いです。東大や京大は抜けていますが、名古屋大学や九州大学もサイエンスでかなり注目されています。
また、企業との共同研究とは別に大学単独の研究成果としての発明届も、毎年100件以上コンスタントに出されています。全国9ブロックの地域大学プラットフォームで募集した最近のギャップファンドへの応募数は、九州・沖縄圏でのエコシステム創出を目指すプラットフォームのPARKS(Platform for All Regions of Kyushu & Okinawa for Startup-ecosystem)が1番多かったと聞きました。そして、その4割程度が九州大学だったそうです。それだけ九州・沖縄エリアのスタートアップの意識が高くなっているということですし、中核として我々が牽引していかなければと感じています。
地域と大学の一体感、よそ者へのリスペクトと温かさがシナジーを生む
仕事の進め方などで、九大発ディープテックで働く良さ、面白さがあれば教えてください。
九州大学と九大OIPのスタートアップ創出や産官学連携活動が、地域の皆さんと共に非常に一体的にできていることが、大きな魅力です。特許や技術移転、スタートアップ、共同研究など、多くの大学は手段ごとに部署や会社が分かれています。
でも九大OIPはひとつの組織の中で産学連携に関わるすべてのことを垣根なくやっています。それは他にあまり例がないように思います。我々のゴールは総合知で社会変革を牽引して世界に貢献することであり、そのための手段は問いません。私は大学の仕事と九大OIPの仕事を兼務していますが、そういう形も両者の関係をスムーズにしている気がします。
市と県もしっかり連携して一体感をつくってくれているので、非常にありがたいです。他の地域ではここまで緊密な連携を経験したことはなく、驚きました。オフィスにもほぼ毎日、市の職員と県の職員が出入りしていて、みんな一緒に楽しくやっています。
そして土地柄なんでしょうか、県外から来た人間に対しても温かく、互いに助け合う感覚の方が多いです。相手のバックグランドをリスペクトして、あなたはこれが得意で私はこれが得意なので、一緒にやったらシナジーが生まれますよね、といった対応なんです。
九大発ディープテックで働くためにご家族を伴って移住される方もいると思います。地域コミュニティへの溶け込みやすさや子育て環境などについて教えてください。
働くにしても住むにしても、とてもいい環境だと思います。自然が豊かで、食べ物もお酒もおいしくて、人も良い。福岡はコンパクトシティと言われていて、都心部から空港へもすぐで移動も便利です。
コミュニティが寛容だという話はよく聞きます。昔から博多港は海外に開かれていたので、そういう気風が根付いているのかもしれません。また、福岡市は支店経済都市と言われるように大企業の支社や支店が昔から多いので、東京から来る方に慣れています。
実際、福岡市は人口が増えていますよね。
娘さんが東京や関西に行くことには難色を示すご家庭も、福岡ならいいよとなるらしく、九州の他の地域から来る人が多いと言われています。つい先日も小中学校の給食費無償化のニュースがありましたし、子育て支援も充実しています。再開発事業の天神ビッグバンも含めて政策が実ってきていて、税収が右肩上がりなので子育て支援に予算をまわせるのでしょう。
トライしやすい副業・兼業OKの「プレCxO」で人材確保に取り組む
九大発ディープテックの課題についてはどのような認識をお持ちですか? そこで働く人が知っておいたほうがいいことや覚悟しておくべきことがあれば教えてください。
課題のひとつは経営人材が不足しがちな点です。大学の研究成果はビジネスの視点から観ると極めてアーリーフェーズでリスクが高いので、初めからフルコミットしづらいんですよね。
そこで、気軽にチャレンジしてもらえるよう、九州大学では「プレCxO」といって起業前から事業化に関われる仕組みを作りました。副業・兼業OKにしたら、全国から300~400人が手を挙げてくれました。
コロナ禍で生まれたリモートワークや副業・兼業を認める流れにも乗ったわけですが、ディープテックに興味を持つ人材がくすぶっていたことがわかりました。7~8割が首都圏の方でしたね。
たぶんみなさん出張等でも福岡に良い印象を持たれていて、出張感覚で始められるなら面白そうといったノリもあるのかもしれません。でも、初めはそれでいいと思っているんですよ。今年もPARKSの枠組みでお声がけしたら800人ぐらいご応募いただいて、だんだんその輪が広がりつつあり、少しずつ、経営候補者人材確保の取り組みも進んでいます。

インタビューは福岡市内にあるいとLab+で行った。高増氏(右側)と古橋氏(中央)、インタビュアーの藤岡(左側)
研究者と産業界のギャップを埋めるコミュニケーターとしての役割
プレCxOの方々には研究者とのコミュニケーションを円滑にとっていただきたいと思っていますが、そこがうまくいかない場合がある点も課題でしょう。研究者と産業界の価値観はスピード感なども含め大きく違うため、経営や事業開発に携わる方がやりづらさを感じることは結構あると思います。
近年だいぶ緩和されてきましたが、国立大学の仕組みもまだ保守的な部分があり、産業界のスピード感や合理的な考え方に十分フィットできていません。それだけに、その間を取り持つコーディネーターが重要や役割を果たします。
同じ言葉でも意味が違うようで、噛み合わないこともあります。先生を引っ張っていけるような人が向いていると思いますし、そんな方に来てほしいですね。
研究者はその研究分野のスペシャリストで、経営候補者は経営や事業開発のプロで、バックグラウンドも違います。互いにないものを持っている者同士なので、リスペクトし合い、感謝し合ってやれるか。そこに尽きる気がします。
九大発ディープテックはどういった方に向いていて、逆にどんな方は向いていないと思われますか?
実際に、ディープテックが解決しようとしている社会課題を体験している方なら、自分事として取り組めるでしょうし、そういう背景を持った人ならちょっとやそっとの壁やギャップは乗り越えてくださると思うので、そういう人にぜひ来てほしいですね。
向いてないのは、受け身になってしまう方。意欲と経歴のある方なら、研究者から事業化の方法について相談される前に、自分事として物事を積極的に考えていって頂ければきっとうまく行くと思います。
最後に、九大発ディープテックで働こうと考えている方々へメッセージをお願いします。
地域と大学が緊密に連携して仲良くやっている環境の中で働けるのは非常にやりがいがあるし、楽しいです。飯はうまいし、人は良いし、自然も豊かで、ちょっと行けば栄えた町がある。これだけ環境的にそろっているところってないと思います。期待して来てください。
スタートアップ支援業務の重要性と素晴らしさを改めて感じることができました。ありがとうございました。
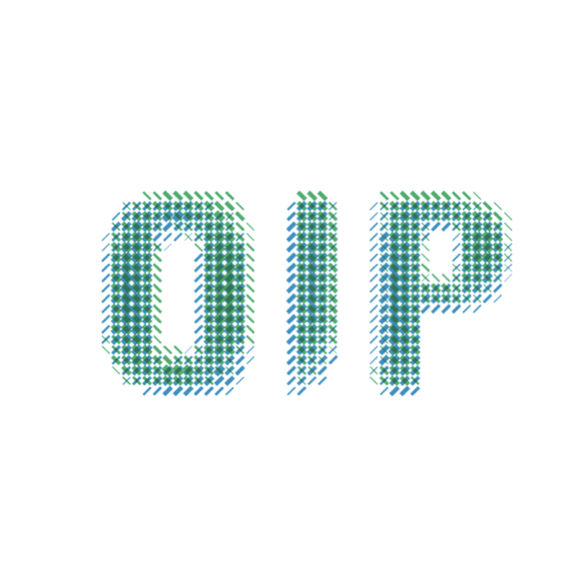
九大OIP株式会社
https://ku-oip.co.jp/
≪MISSION≫
九大OIPは、九州大学の産学官連携を
先導する組織である。
われわれは、大学の教育・研究の向上に資する
産学官連携活動を支援する。
≪VISION≫
九大OIPは大学と社会とのインターフェースとして、
九州大学が起点となるエコシステムの構築を目指す。
≪事業概要≫
① 成果活用促進事業(共同・委託研究等の企画・あっせん)
② 研究成果活用事業(コンサルティング及び研修・講習に関する業務)
・大学等の研究成果を実用化するために必要な共同・受託研究等を企画・あっせんする業務
・共同・受託研究等プロジェクトのマネジメント業務
・大学等の研究成果を活用したコンサルティング、研修・講習等業務
・大学等の研究成果を産業技術として企業に移転する業務
・大学等の研究成果を活用したベンチャー企業の創出・育成支援 など
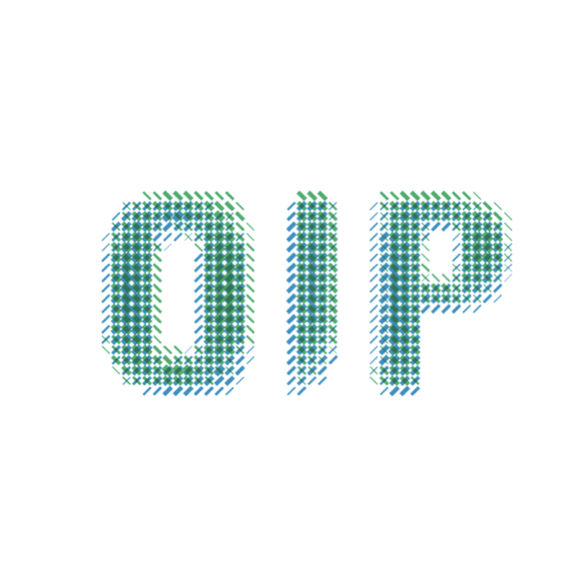
九大OIP株式会社
https://ku-oip.co.jp/
≪MISSION≫
九大OIPは、九州大学の産学官連携を
先導する組織である。
われわれは、大学の教育・研究の向上に資する
産学官連携活動を支援する。
≪VISION≫
九大OIPは大学と社会とのインターフェースとして、
九州大学が起点となるエコシステムの構築を目指す。
≪事業概要≫
① 成果活用促進事業(共同・委託研究等の企画・あっせん)
② 研究成果活用事業(コンサルティング及び研修・講習に関する業務)
・大学等の研究成果を実用化するために必要な共同・受託研究等を企画・あっせんする業務
・共同・受託研究等プロジェクトのマネジメント業務
・大学等の研究成果を活用したコンサルティング、研修・講習等業務
・大学等の研究成果を産業技術として企業に移転する業務
・大学等の研究成果を活用したベンチャー企業の創出・育成支援 など
