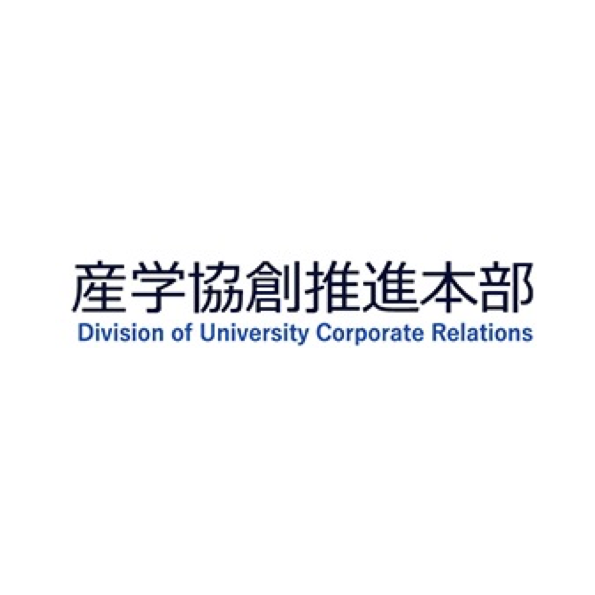いち早くスタートアップの創出・支援に取り組み、業界の礎を築いた東京大学。同大発スタートアップは毎年40〜50社ペースで設立され、圧倒的な数を誇っています。東京大学産学協創推進本部は現在、株式会社東京大学TLO、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社(東大IPC)、株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ(UTEC)と緊密に連携して活動。地球規模の課題解決に貢献することをめざしています。
2009年から同大学でスタートアップ支援に取り組む、東京大学産学協創推進本部の菅原岳人氏にインタビューしました。スタートアップ黎明期の日々からディープテックスタートアップが直面する課題まで、多くのお話を伺いました。広い視野で世界の課題や日本経済、業界全体について考える菅原氏からは、フロントランナーとしての自負と信念が感じられました。

スタートアップ推進部 ディレクター 特任研究員
菅原岳人氏
2009年よりインキュベーションおよびアントレプレナーシップ教育担当として東京大学のスタートアップ・エコシステム形成に従事。学内の起業相談から各種支援プログラムの企画・運営、インキュベータ本施設管理、教育プログラム群の運営などを担う。前職はIT系コンサルティング・ファーム。東京大学大学院経済学研究科修士課程修了。
- 目次 -
世界を見据え、2004年の国立大学の法人化を機に組織的支援をスタート
まず、東大産学協創推進本部の主なミッションと取り組みについて教えていただけますでしょうか。
産学協創推進本部は大学と産業界との広範な産学連携をミッションにしていて、既存企業や他の研究機関などとのコラボレーションや知財関連を広くカバーする本部組織です。その中でスタートアップ推進部は、社会的にも経済的にも大きなインパクトをもたらすスタートアップを大学から生み出すための支援と、広い意味でのアントレプレナーシップ教育をミッションとしています。
2004年の国立大学法人化で、既存企業に共同研究や知財のライセンスを通じて大学の研究成果を事業化してもらうだけではなく、スタートアップによる研究成果の社会実装というパイププランを持つべきだという流れができました。現在では日本のスタートアップは全国に2万4千~2万5千社ぐらい、資金調達しているのが1万社ぐらいというのがこの業界の世界観ですが、2004年当時はもっと少ない社数しかありませんでした。日本ではスタートアップの中で大学発の割合が高くなっており、それは技術で世の中に大きなインパクトを与えてほしいという期待の表れと受け止めています。
東大産学協創推進本部の実績について教えていただけますでしょうか。
東京大学は「東大発」の認定はしていません。大学の研究成果をコア技術として活用していたり、在学生が起業したスタートアップは、大学が把握できている範囲で2024年度末時点で577社あり、IPOが27社、M&Aが66社という内訳になっています。
他と比べると圧倒的な数ですね。理由は何だとお考えですか?
最も大きな理由は単純に始めるのが早かったことだと思います。国立大学法人化を受けて、全国の大学で大学発スタートアップ支援が動き出しましたが、本学はその準備のために2年ぐらい前から、産業界から10人以上の有識者を集めて議論し、産学連携本部(現・産学協創推進本部)をつくるために動いていました。インキュベーションシステムと投資機能のためにUTEC(株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ)を作ることになりました。そして、重要な知財ライセンスをスタートアップにとって使いやすくするために、当時すでにあった東大TLOの完全子会社化も進めました。当時そこまで強く推進しようとする大学は少なく、本学も少人数のチームでしたが、先立って始めたことで、失敗も含め多くの知見を得た結果だと思います。
なぜ東大はそんなに早い段階からスタートアップ支援を始めたのでしょうか?
本学が常にグローバルな視点で世界を見ていたことが大きな理由だと思います。アメリカでは、いわゆる重厚長大の大企業の経営が悪化して新興のテクノロジースタートアップが経済を引っ張る構造が日本より20年ぐらい早くできていて、その状況に大学が大きな役割を果たしていました。そして、日本もいずれ同じような構造変化が起きてスタートアップの重要度が大きく増加するパラダイムが、起こり得るシナリオのひとつとして想定されていました。当時の本学首脳陣がそうしたグローバルのベンチマークをもとに、日本の産業を支えるために始めたのではないかと思います。
日本経済に対する危機感と信念が7年間におよぶ苦しい日々を支えた
研究をビジネスにすることについて、反発も大きかったのではありませんか?
法人化前に大学発ベンチャー1000社構想があったとき、そこそこの数の大学発ベンチャーができました。ただ、そのほとんどはビジネスの体を成しておらず、批判されましたし、学内でも議論になりました。中にはベンチャーに対して良い印象を持っていなかった先生方も少なくなかったと思います。2004年からリーマンショックを挟んで2011年ぐらいまでの約7年間は、昨今のスタートアップ環境と比較すると冬の時代だったかもしれません。大学発スタートアップへの世の中からの注目度は今ほど高くなく、ごく少数の先生だけが起業に取り組んでいました。我々はひたすらインキュベーションを行い、地べたを這いずりまわって活動しましたが、スタートアップに挑戦する人の数は今の半分以下だったと思います。
リーマンショックから回復する頃になって、モルフォ、ユーグレナ、ペプチドリームなどがIPOしてから潮目が変わってきました。実は大学発ベンチャーはVCから見てもリターンの大きい投資先になり得るし、結構イノベーティブなことをやっているじゃないか、と見方が変わってきたんです。その後3年ぐらいかけて成功事例が増え、潮目が変わったのは2014年頃でしょうか。UTEC以外のVCも積極的に投資を始めましたし、政府が中期計画を出してスタートアップ支援を強化されることになりました。そして、ここ10年ぐらいが一番盛り上がっています。
苦しい7年間を耐え切れた理由は何だったのでしょうか?
海外の大学と交流のある方など、リスクをとって誰かがやらなければいけないという信念を持った先生方や起業家が少数ながらいらっしゃいました。私たちとしても、スタートアップを生み出せないと日本経済の行く末はないと思う時期でした。逆説的ですが、当時は経済状況が悪くてスタートアップに一喜一憂しているどころではなかったので、落ち着いて活動できました。ここでIPOを出すなど海外で名が通るようなスタートアップを生み出せたら良いニュースになると思って頑張れた時期でした。
東大がそういう姿勢を示したことは、すごくいいメッセージになったのでしょうね。東大が諦めたら、他はどうなっていたかわからないですよね。
東大でできなかったら他大学もできないのではないかといった空気感はありましたね。様々な形でサポートいただいた行政の方々からも、成功事例を出すよう暗にプレッシャーを感じていました。いまスタートアップ創出に力を入れている他の大学も、急に成功事例を出すように言われても難しいと思います。かといってハードルを下げてやみくもに投資してもリソースが分散してしまうので、まずはふさわしいと考えるスタートアップをサポートして成功事例を出すと好循環が回り始めるのではないかと思います。

2007年開所以来多くの東京大学関連スタートアップが育ったインキュベーション施設「東京大学アントレプレナープラザ」。ペプチドリームなど6社のIPOを含む数十社が巣立っていった。
国内で競い合うのではなく、世界で戦えるスタートアップを日本が生み出すことが大事
菅原さんの簡単な略歴と、東大でスタートアップ支援に携わるようになった背景を教えていただけますでしょうか。
本学在学中からスタートアップやイノベーションに興味があって、学士論文も修士論文もスタートアップ関連がテーマでした。大学院を出た後は就職してコンサルタントをしていましたが、いつかスタートアップをやりたいとずっと思っていました。2009年に前任者から打診があり、考えていた起業はやめてここに来ました。肩書の変更はありましたが役割は最初から変わらず、我々の部署の2大ミッションであるスタートアップ支援とアントレプレナーシップ教育をずっと担当してきました。
東大発ディープテック・スタートアップの特徴があれば教えてください。
どこの大学発かは意識しなくてもよいと思っていて、東大発にはこだわっていません。私たちの役割は、テクノロジーで社会に貢献できて、なおかつビジネスにおいても競争力のあるスタートアップを生み出すこと。自動運転向けのオペレーティングシステムを開発するユニコーン候補の株式会社ティアフォーは名古屋大学発で、創業者の加藤真平先生はのちに東大に移られています。先生のような方が、いろいろな大学のテクノロジーローラーとして活躍されるのは当たり前であるべきだと考えています。コロナ治療薬を開発したモデルナが買収したオリシロジェノミクスは立教大学発ですが、東大の研究室とも連携し、早稲田大学にもラボを持っていました。どこ大学発というカテゴライズに固執するのではなく、大学や企業のテクノロジーをロールアップして価値を高めることが目指すべきところだと考えます。東大関連のスタートアップは日本でのIPOがほとんどですが、M&Aは海外の会社に評価されて買収される例が結構多いので、もっと価値を高めてバイアウトされてもいいし、買収してグローバルに戦っていける会社になってもいい。そういう思考を持っているところが特徴かと思います。
分野的な偏りもあまり意識していません。研究分野や先生の強みにフォーカスするやり方もありますし、将来を見据えて市場拡大が見込まれる分野に力を入れるやり方もあります。今ならサステナビリティやクライメートテックなどのトレンドもあります。本学は総合研究大学なので、ライフサイエンス、ロボティクス、宇宙などいろいろな分野に強い先生がいらっしゃいます。総長の言葉を借りると、「地球規模の課題を解決する」。それに貢献する研究成果があれば、積極的に社会実装できる方法を探すのが私たちの使命です。どの分野でも強くなっていくためには、東大だけにとどまらないことを今まで以上に意識していくべきだと考えます。
250社以上が集まる“本郷バレー”は、多くを仲間と分かち合える場所
東大関連のディープテックで働く魅力を教えていただけますか?
ディープテック領域の会社は、急成長して利益を出すことが第一義ではなく、時間とお金がかかっても解決したい課題があり、社会を良くしたいというミッションドリブンの会社も多いと思います。ですから、この課題を解決したい、社会のこういう人たちの生活を良くしたい、といった考えを持つ人にとっては非常にやりがいがあるのではないでしょうか。また、研究者との接点があり、最先端の研究や技術に触れられる点が魅力だと思います。スタートアップ登場前は、ディープテックが商用化されて普及するプロセスを見る機会はほとんどありませんでした。ディープテックのすべてを見て関われる場所は、スタートアップだけだと思います。
ディープテックには限りませんが、本郷キャンパス内と周辺には250社ぐらいのスタートアップがあり、そのうち100社以上は東大関連の会社です。仮に入ったスタートアップが合わなくても周りに他のところが多くあるので気軽に移ることもできます。例えば私が本郷通りのカフェのテラスに1時間いたら、その間に10~20人はスタートアップの起業家やベンチャーキャピタリストが前を通り、挨拶を交わすでしょう。従業員同士も知り合いが多いので、「うちの会社、資金調達したところで人を募集してるんだ」といった会話が日常的にあります。飲食店で食事をしているときに、横でスタートアップの人たちの話が聞こえることも多いです。仲間がたくさんいるので、興味がある人は東大周辺に来てほしいですね。

シードステージ向けのインキュベーション施設「東京大学アントレプレナーラボ」内にある共用バイオ実験室。大きな割合を占めるライフサイエンス系スタートアップ向けに、シェアラボ機能を提供している。
本来的な役割を果たすため、ビジネスのスケールアップが喫緊の課題
東大関連のディープテックスタートアップにはどんな課題があると認識されていますか?
海外のスタートアップ支援をベンチマークしてきた私たちは、2010年代前半ぐらいのリーンスタートアップ的な手法を積極的に取り入れ、大学発スタートアップ支援にも適用してきました。その結果、ある程度の数をコンスタントに出せるようになりましたが、最近は世界的なスタートアップの大型化、日本のIPO市場の天井にキャップがかかるといった問題があります。
本来スタートアップは、急速に成長してテスラのように10~20年ぐらいで大企業と遜色ない影響力を持つことが期待されています。しかし、残念ながら日本ではまだそこまで行っておらず、今まさにスケールの壁にぶつかっているところです。
特にディープテック領域では、ある程度早く立ち上げてそこそこのスタートアップをたくさんつくるという方法論から、インパクトのあるスタートアップをどう生み出すかという考え方に変わるよう求められていて、そこでもがいているところです。どんな戦略なら本来の役割が果たせるのか、スタートアップ業界全体として、もう一段スケールアップさせなければいけないことが喫緊の課題です。
ディープテックを含む技術系も、日本でIPO可能なサイズにすることはできるようになってきましたが、それだと一段足りません。ウェブ全盛期は、とりあえず新しいプロダクトを早く出して、ダメだったらイタレーションによってPMFを達成するというのが王道でしたが、最近はカンパニークリエーション(企業創出)のような方法論が出てきて、戦略を練ってグローバルマーケットを見定めなければいけなくなってきています。いまは、マーケットを見ることができて、かつ研究者と対話できる人が求められています。
強力なサイエンスをベースに商品化を考えるのがひとつの東大型の成功事例で、それが得意な人はいます。ただ、それだとスケールが足りないです。
最近来る起業家の方々の話を聞くと、テーマがそこまで大きくないケースもあります。技術を使えばある程度成功でき、その人にとっては十分な課題解決になると思いますが、私たちとしては、もう少しマクロな目線で地球規模の課題を解決できるビジネスにしてほしい。でも最初に考えたビジネスのサイズを大きくするのは結構難しく、起業家のキャパシティや能力だけに頼ってしまうと、それが全体のキャップになってしまう。既知の市場でスケーラビリティを追求してそれだけに頼っても数が限られてしまうので、場合によっては市場がまだないところにマーケットをしっかりクリエイトしていく人材も必要です。2024年にIPOした宇宙ベンチャー、アストロスケールの岡田光信さんのような起業家はその一例かもしれません。
事業化について研究者と足並みをそろえることは、難問であり醍醐味
よくある東大スタートアップでの採用ミスマッチの事例と、そうしたことが起こらないためのアドバイスがあればお願いいたします。
東大に限ったことではないですが、スタートアップでは大企業なら当たり前の環境が整っておらず、最初にお願いした業務以外の仕事もやってもらわざるを得ない場面が多々あります。IT系は比較的みんな元気で柔軟性がある印象ですが、例えばテック系に採用された優秀なエンジニアなど、中には決められた業務だけをやりたいという人もいます。ディープテックとはいえスタートアップなので、職種を問わず柔軟性を持って来て頂けるとよいと思います。
多くの大学で、技術の事業化について研究者と話をする難しさについて聞きます。東大ではいかがでしょうか。
技術のことを一番わかっているのは研究者です。ただ、その技術をビジネスにすることはまた別問題です。それをどう説明して理解してもらうかは永遠の課題だと思います。海外の大学も含め、この課題には20年間向き合っています。非常に高度な素晴らしい技術であっても、技術にこだわりすぎるあまり、超ニッチなプロダクトになってしまうこともあります。研究者と事業化の面でどう目線を合わせるか。難しいですがここがうまくできると最強になるので、ディープテックの楽しいところでもあると思います。
最後に、東大発ディープテック・スタートアップで働こうと考えている人に、背中を押すようなメッセージをいただけますか?
以前のスタートアップには、ブラックなイメージがあったと思いますが、現在は一般企業と遜色なくなりました。大学発ディープテックとなるとそれなりのスキルレベルを求められるので、待遇面は心配しなくて良いでしょう。また、現在の大学発のディープテックスタートアップにはミッションドリブンで社会課題を解決したい人が多く集まっています。
また、職場を移りやすいという点では、本郷の環境はおそらく日本一です。周辺企業を渡り歩いていろいろな人と情報交換する中で、自分の立ち位置や価値観が定まってくると思います。どこに行くべきか迷う方もいらっしゃると思いますが、私たちのような支援組織やベンチャーキャピタルもたくさんあります。興味のある方は、怖がらずにこの世界に飛び込んできてほしいです。
ありがとうございました。