
東京は、日本の経済・技術の中心地であり、大学発スタートアップの数が日本一を誇るイノベーションの拠点です。特に、AI、ロボティクス、バイオテクノロジーなどのディープテック分野では、東京大学や東京工業大学をはじめとする研究機関から次々と革新的な技術が生まれています。資金調達の環境や企業との連携も進み、スタートアップは国内市場にとどまらず世界に展開。本記事では、東京のディープテックスタートアップの最前線に迫ります。
- 目次 -
トップランナーとして産学協創を牽引|東京大学 産学協創推進本部
いち早くスタートアップの創出・支援に取り組み、業界の礎を築いた東京大学。同大発スタートアップは毎年40〜50社ペースで設立され、圧倒的な数を誇っています。東京大学産学協創推進本部は現在、株式会社東京大学TLO、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社(東大IPC)、株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ(UTEC)と緊密に連携して活動。地球規模の課題解決に貢献することをめざしています。
2009年から同大学でスタートアップ支援に取り組む、東京大学産学協創推進本部の菅原岳人氏にインタビューしました。スタートアップ黎明期の日々からディープテックスタートアップが直面する課題まで、多くのお話を伺いました。広い視野で世界の課題や日本経済、業界全体について考える菅原氏からは、フロントランナーとしての自負と信念が感じられました。

【東京特集】フロントランナー、トップランナーとして産学協創を牽引。大きなインパクトとスケールを持つスタートアップ創出に挑む
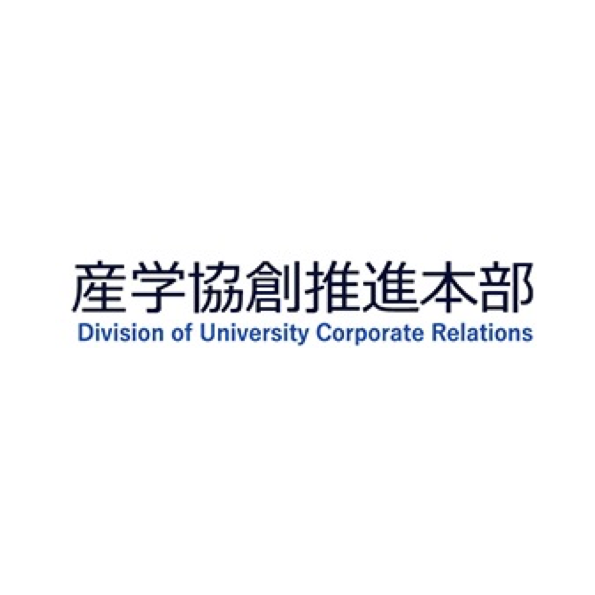
東京大学 産学協創推進本部スタートアップ推進部 ディレクター 特任研究員 菅原岳人氏
産業創造を目指すディープテック支援の新手法|みらい創造インベストメンツ
単なる投資にとどまらず「産業創造」を目指すベンチャーキャピタル、みらい創造インベストメンツ。技術・ビジネス・金融の三位一体で新産業を創出する独自の「ベンチャークリエーション」手法で注目を集めています。自身も起業・エグジット経験を持つ執行役員の高橋遼平氏に、ディープテック支援の実践と東京科学大学発スタートアップの可能性について伺いました。

【東京特集】産業創造を目指すディープテック支援の新手法

みらい創造インベストメンツ執行役員/パートナー 高橋遼平氏
「自分の未来は自分で創る」アントレプレナーを育む|早稲田大学 アントレプレナーシップセンター
早稲田大学は、学生・教員、研究者の起業家精神を育み、特許技術や研究成果を活用したベンチャー企業の育成を通じて、イノベーションの創出に取り組んでいます。石井裕之氏が所長を務めるアントレプレナーシップセンターはこうした取り組みの最前線にあり、起業したい学生や教職員、卒業生に対してさまざまな支援を行っています。本インタビューで強く印象に残ったのは、石井氏の早稲田愛とスタートアップへの熱い思いです。早稲田発スタートアップで自分のキャリアを磨きたいと考えている方にとっては、非常に興味深い内容となっています。

【東京特集】「自分の未来は自分で創る」早稲田のカルチャー

早稲田大学 アントレプレナーシップセンター所長 石井 裕之氏
