
福井大学では2019年10月から、地域企業とのプロジェクト型共同研究を推進するため「産学官連携コンシェルジュ」を配置し、地域企業とともに、未来を拓く「技術開発」と「人材育成」に取り組んでいます。
本インタビューでは、米沢氏のスタートアップ人材の育成にかける思いや福井で大学発スタートアップで働くことの魅力について詳しくお話を伺いました。

福井大学 産学官連携本部 本部長
米沢 晋氏
1988年 京都大学工学部工業化学科卒業
1990年 京都大学大学院工学研究科修士課程工業化学専攻修了
1992年 福井大学・助手(工学部)
2003年 福井大学・助教授(工学部)
2010年 福井大学産学官連携本部・教授
2012年 福井大学産学官連携本部長
2025年 福井大学理事(社会共創、企画戦略、広報担当)/副学長
(現在に至る)
無機フッ素化学および電気化学に基づく、次世代電池材料やナノめっき技術、光学材料等に関する研究を実施するほか、地域企業等との共同研究や産業人材育成に注力しつつ、地域における産学官金連携の仕組みづくりを牽引している。
産学官連携本部
https://hisac.u-fukui.ac.jp/
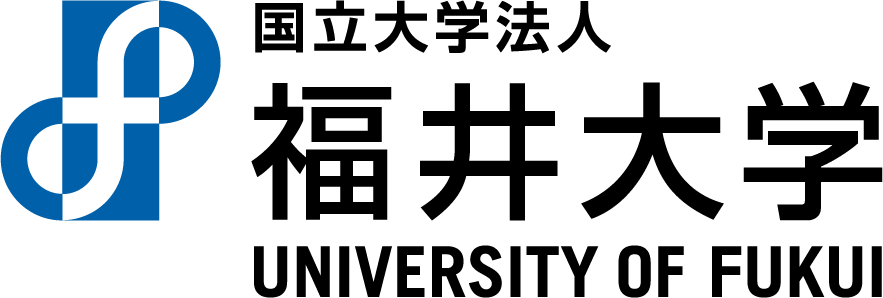
国立大学法人 福井大学
https://www.u-fukui.ac.jp/
≪大学理念≫
「格致(かくち)によりて 人と社会の未来を拓(ひら)く」
近代福井の礎(いしずえ)を築いた松平春嶽公の揮毫による本学所有の「格致」の額面は、同人の歴史的功績を考えれば本学の宝であると言えます。「格致」とは「物事の道理や本質を深く追求し、理解して、知識や学問を深め得ること」という意味です。
本学学生にとっては、学びと人格育成に際し、また教職員においては、研究・教育・社会貢献等で自らの指針となる語句です。我々は、この語句を旨とし、県内より世界に至る様々な地域において、そこに集う人、ならびに社会の未来を拓くことに主体的にかかわり、貢献することを目指します。
- 目次 -
アントレプレナーシップの土壌を持つ福井というまち
福井大学 産官学連携の支援の取り組み内容や、特徴についてご紹介をお願いいたします。
福井大学では、産学官連携の中で地域のイノベーターな経営者の方々との対話を重ねながら、そこに教員や学生を巻き込み、自分がアントレプレナーとして立ち上がろうと思う人の数を増やす努力を続けています。
産学官連携に関しては、金沢大学や信州大学などが先進的な取り組みをしています。特に信州大学は、大学としての「色合い」、ディープテックに対する距離感といった点で、我々と近いものを感じています。福井は繊維産業が盛んな地域なので、信州大学に繊維学部が残っていることも近しさを感じる理由の一つです。
福井大学が金沢大学や信州大学、あるいは筑波大学と大きく異なる点は規模、すなわちネタ(アイデア)の数ではなく、人材の数が少ないということです。
スタートアップというのはダーウィン的な生き残りの世界で、多くの挑戦者の中からわずかに生き残ったものだけが成功を収める世界。そう考えると、そもそもの人数が非常に少ない福井地域は不利だとは思います。
ただ、福井は、中小企業、研究開発型のものづくり企業が数多く集積している地域でもあります。
歴史的に繊維機械産業が盛んで、メガネフレームに代表される金属加工・樹脂加工といった分野も強く、出荷額で見ると、高分子や無機セラミックス系の化学分野も大きな割合を占めています。世界や国内でのシェアが上位の製品や、オンリーワンの技術を有する企業も数多くあり、その情報を「『実は福井』の技」というサイト(https://info.pref.fukui.lg.jp/tisan/sangakukan/jitsuwafukui/
)で紹介しています。
新しいものを作って世の中を変えていくことに意識が高い人が多く、社長の輩出率は全国1位(※)。戦後に創業して2代目、3代目へと続いている会社などは、代替わりの度に経営の見直しを経験していますし、そういう意味ではアントレプレナーシップの土壌を持っているといえます。
一方で、企業側が強いがゆえに、共同研究の中で生まれた事業化のアイデアが、企業の事業展開に引っ張られる傾向があるのも否めません。研究者も、自ら起業するよりも地域のアントレプレナーに情報を提供したほうが効率的だという考えが強い。
真面目で目立つことを好まない県民気質もあり、「自分が中心になってスタートアップを引っ張っていこう」という人材がなかなか現れてこないのが課題です。
※帝国データバンクの「全国社長『輩出率』調査(2023年)」によると福井県は3年連続で1位。
「研究の成果を社会へ」自然と拓かれた産学連携の道
米沢さんが産学官連携本部長として地域産業の活性化や人材育成に注力され、地域の課題解決に取り組むに至った背景について教えて下さい。
私自身はずっと研究畑で企業経験はありません。ですが、私の前任の教授が産業技術総合研究所の大阪工業技術試験所を経て、旧通産省時代に産学連携のプロジェクトを任された方でした。
その方と一緒に仕事をしているうちに私も経済産業省や科学技術振興機構(JST)とのつながりが増え、研究成果を社会に展開していくことに面白さを感じるようになりました。
そもそも大学は人と人とのつながりの場で、研究者は学会などを通じて国内だけでなく世界にネットワークを持っているのですから、これを使わない手はないと以前から感じていました。
工学の研究は、世の中に成果を出して、フィードバックを次の研究テーマに落とし込みながら技術をブラッシュアップしていくことが大切です。これを私は「マテリアル・ベンチマーク・ループ」と呼んでいます。これは、研究で生まれた技術シーズ(材料)を企業などに評価(ベンチマーク)してもらい、そのフィードバックを次の研究開発に活かして循環(ループ)させていくという考え方です。
学生に対しても「研究テーマで大切なのは新規性と進歩性。そして、マテリアル・ベンチマーク・ループを産学で回しながら、世の中に役立つ技術に磨き上げていくことが大事だ」という指導を続けてきました。そうした活動が認められて、産学連携本部長に声がかかり、現在に至ります。
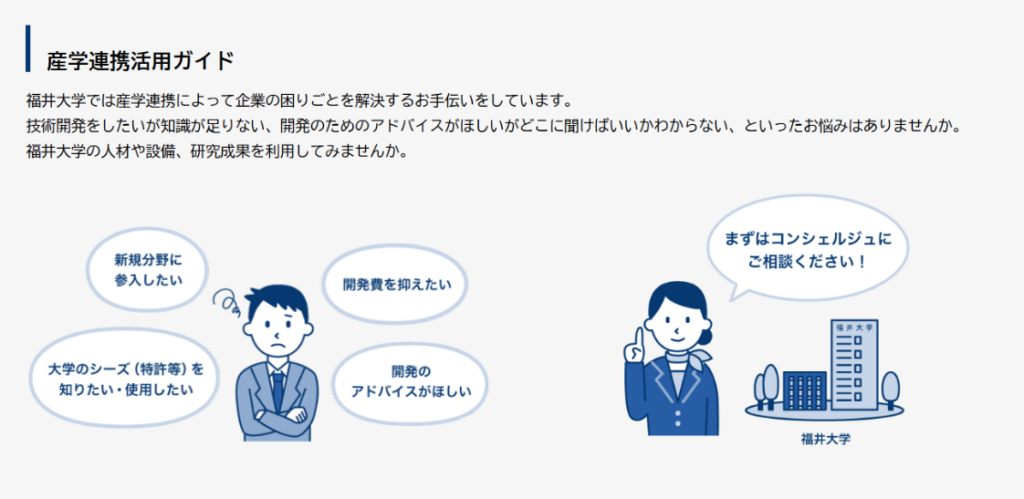
「スモールビジネス」「万事相談」という支援スタイル
福井大学発ディープテック・スタートアップの特徴、将来性(ポテンシャル)・世界からみた強み、について教えてください。
特許が出てから実際に社会実装されるまで、少なくとも10年はかかるといわれています。ディープテックならさらに時間がかかるでしょうし、コストも莫大なものになります。ですから、ユニコーン企業を目指しつつも、周辺領域にあるスモールビジネスに地道に取り組んでいくことで、起業する人の数を少しずつ増やそうとしています。
とはいえ、東京大学の「エッジ型産学連携(※)」のような大掛かりな取り組みは福井大学では難しい。そこで、スモールビジネスを切り出して学生の演習課題にするなど、MOT(技術経営:Management of Technology)に早くから取り組んできました。
ポテンシャルという点では、繊維系、金属加工・樹脂加工系、高分子や無機セラミックス系など、地域に紐づいた分野がたくさんあります。また、大学には知能システム工学やロボティクスの研究者もいるので、その辺りは実は狙い目だと思っていますし、AI画像解析も企業シーズになると考えています。
一定の要件を満たして認定された企業は「福井大学発ベンチャー」の称号を5年間使用することが可能で、すでに11社が認定されています(2025年5月現在)。
大学発を名乗ることで対外的な信用度が高まりますし、大学を法人登記場所にすることも可能です。大学設備も使えるよう、産学官連携本部が中心となって柔軟な運用を行っています。数が少ないからこそ「万事相談で」と個別対応で運営できるのが大きな特徴です。
※文部科学省が推進する、次世代のアントレプレナーを育成するプログラム「EDGE-NEXT(Exploration and Development of Global Entrepreneurship for NEXT generation)」などを指す。
「技術も情熱もある」それでも立ちはだかる“スタートアップの壁”
福井大学発スタートアップの課題について教えて下さい。
一番の課題は人材の少なさです。まず、経営人材の不足。CTOはいてもCEOになれる人材がいません。
スタートアップの社長というのは、ある程度“はっちゃける”くらいのスケールの大きな人が向いていると思うのですが、大学発スタートアップでは、そのあたりにミスマッチが生じるケースが多いように思います。
教員が「やむを得ずCEOを務めている」というパターンはもちろんのこと、CTO的な教員がいたとしても、その教員が持つ知的財産や技術シーズは教員個人からうまく切り離さなければなりません。思い入れが強すぎて技術を守ることを優先しがちになるからです。
また、“夢の技術”をどう社会実装するか。一般企業のような「市場を見極める目」や「事業展開に関する知見」を持たないために苦労することも多々あります。これは、福井大学だけに限らず、多くの大学発スタートアップに共通する悩みではないでしょうか。
資金調達も非常に大きな課題です。地方になれば億単位の投資を支援してくれる企業は少なくなります。
ディープテック領域はもちろんのこと、繊維分野などで小さな規模からスタートするとしても、初期投資は数億円規模になることも珍しくありません。そのような巨額の初期投資をどうクリアするか。現時点では、私自身も有効な解決策を見いだせていません。
こうした課題を抱えつつも、本当に魅力的な取り組みが次々に生まれています。例えば無水染色技術を持つスタートアップや、小型のフルカラーレーザープロジェクションモジュールを開発し、網膜に直接スキャンできるスマートグラスの実用化を目指すスタートアップ、「超小型人工衛星」のプロジェクトなど。
「一般企業に勝るとも劣らない技術力と情熱を持っているのに」と思うと、課題がなかなか解決できないことにもどかしさを感じます。
日本ではまだ「失敗を許容する文化」が根づいているとはいえません。一方で、大学は「失敗を許容できるエリア」です。そういう大学発スタートアップにぜひ投資をしてもらいたいと思います。

四季の変化に富んだ魅力的な土地で起業仲間を増やしたい
最後に米沢さんから、福井発ディープテック・スタートアップで働こうと考える人へメッセージをお願いします。
福井は「スタートアップの仲間が多い地域」であることが大きな魅力です。中小企業の社長、アントレプレナー、イノベーターが多く、そういった方々と直接話をしたり、アドバイスを受けたり、一緒に仕事をしたりする機会が多いというのは、福井ならではの魅力だと思います。
ロケーションの良さも福井の魅力です。アクセスもよくなり、福井から京都や名古屋へは電車で1時間〜1時間半ほど、大阪へも2時間かかりません。
東京までのアクセスも北陸新幹線延伸により、乗り換えなしで移動できるようになり便利になりました。高速道路網も整備されており、物流の観点からも主要都市へのアクセスがしやすい地理的条件を備えています。
職場環境としては、職住近接なのはとても働きやすいと感じます。通勤に15分もかかると「長いね」と言われるくらい(笑)。
四季折々の変化に富んだ地域なので、そうした変化を楽しめる人も向いていると思います。常に視点を変えて試行錯誤する研究者にとっては、四季の変化も一つの良い刺激になるのではないかと思います。
福井にはスタートアップの土壌と産学連携の歴史、そして豊かな自然環境があります。ともに歩めるスタートアップ仲間が一人でも増えると嬉しいですね。
貴重なお話、ありがとうございました。
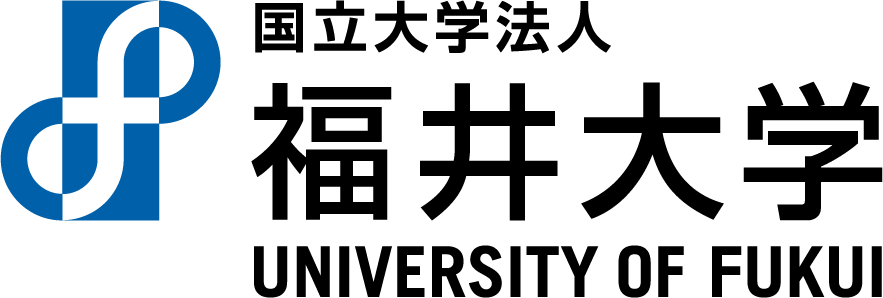
国立大学法人 福井大学
https://www.u-fukui.ac.jp/
≪大学理念≫
「格致(かくち)によりて 人と社会の未来を拓(ひら)く」
近代福井の礎(いしずえ)を築いた松平春嶽公の揮毫による本学所有の「格致」の額面は、同人の歴史的功績を考えれば本学の宝であると言えます。「格致」とは「物事の道理や本質を深く追求し、理解して、知識や学問を深め得ること」という意味です。
本学学生にとっては、学びと人格育成に際し、また教職員においては、研究・教育・社会貢献等で自らの指針となる語句です。我々は、この語句を旨とし、県内より世界に至る様々な地域において、そこに集う人、ならびに社会の未来を拓くことに主体的にかかわり、貢献することを目指します。
